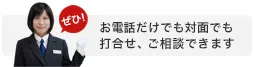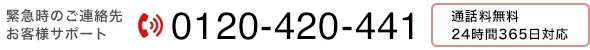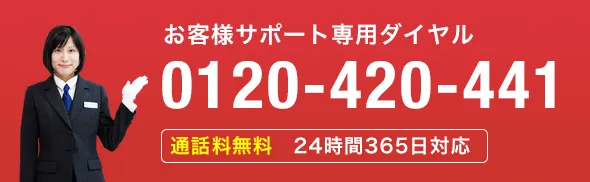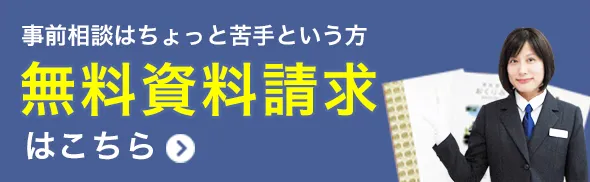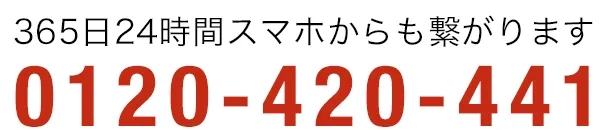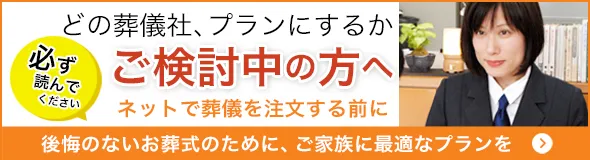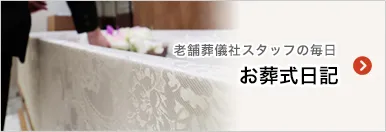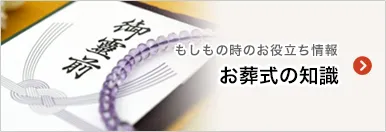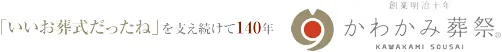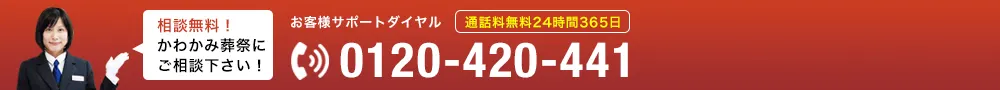こんな対応も
12月だというのに、こんな暖かくて、ちょっと変な感じですね。
さて、そんな年末にこんな出来事が。
マイカーの車検を受けましたが、いつもは正規ディーラーにて受けていたのを、ちょっと価格もやすく、日程の融通も効くとのことで、あるカー用品専門の大手さんにお願いしました。
1日で車検は終わり、証明のシール?フロントガラスに貼るあれです。あれが、一週間 くらいかかるということで、仮のシールを貼り付けてくれと。郵送でシールが届く手配をしてその日は、終了しました。
さて、フロントガラスの、仮シールの期限がきても正式なシールが届く気配がない。年末でる忙しいからか、と仕方なく黙って待っていましたが、数日しても届く気配も何もない。これでは車に乗ることすらできないのでは?と連絡を入れたところ、「すみません、まだ郵送の手配できてなくて、すぐ送りますね」との返答。
送る?この人は一体何をいっているのだろう?と疑問に思い、「ちなみに車に乗りたいのだが、何かあったら、全てそちらの責任ですと警察には伝えれば良いのですね。そうすれば、警察は見逃してくれるのですね。わかりました。であれば、郵送してください」と。
ちょっと突っ込んでしまいました。
私にはわかりませんが、別にちゃんと車検通してるから、いいじゃんって感じなのか、よくあることなのか知りませんが、郵送で済ませようとしたことに疑念が湧きました。
単発のお客さんだからの対応か?正規のディーラーでは考えられない対応に、差を感じてしまったことは否めません。
担当の方にも嫌な思いをさせたかもしれませんが、大きなクレームがでないことを祈り、また自身の仕事にも置き換え、他人ごとではないと、思うのです。
皆さん大掃除の時期になって来ましたが、今年は本当に暖かい日が多いですね。
しかし間違いなく今年も残りわずかです。
一年の誇りをとり新しい年を迎えたいとお考えの方が多いと思います。
そんな掃除用品がひとつ10円で購入できるとしたらいかがですか?
あるんですそんな場所が
当社の大池橋店で今月19日の10時よりチャリティバザーを開催します。
お近くの方はぜひお越しくださいませ。
売上金は全額寄付をさせていただいて降りますので、
皆様のご協力をお願いします。
忘年会シーズンですが、今年もすでに盛り上がっているようで仕事の帰り道などで忘年会終わりだろうと思われる団体さんとすれ違うことも日に日に増えているように思います。
かく言う私も毎年恒例の友人や会社などすでに数件のお誘いを受けており、今から楽しみにしています。
しかしながら全部が楽しいで終われば良いのですが、中には飲み過ぎ食べ過ぎやハメを外し過ぎて少々しんどそうにされている方もチラホラ…
やはりお酒の場ですし何より一年の締め括りの場ですので、せめて最低限の節度は保って楽しみたいものです。
皆さんはこのシーズンどのようにお過ごしでしょうか?
飲み過ぎには充分に気をつけてこの年末をお過ごし下さいね!
本当に寒くなってきました。身体のふしぶしがかたくなってきているのがわかります」。こんなとき身体を急に動かしたりするとけがをしやすくなります。特にスポーツをするときなど夏の準備運動では不十分で変ひねったりなど。その時その時に合わせてアップすることが大切です。
日々の業務にも通ずるものがあると思うのですがその時その時でマニュアル通りではなく少し変更した方がいいこともあります。たとえばお客様へお送りするお手紙など。1つ1つの作業を確認しながらしていこうと思います。
浄土真宗では、戒名のことを法名と言います。法名について少しお話しします。
法名は、付けたからといって極楽へ往けるものではありません。法名とは、真の仏弟子が生前、仏教の師匠から頂く名前のことを言います。
またお釈迦さまは、本当の幸せになった人のことを私の親しき友であると仰っています。お釈迦様は幸せになった人を「私の親友だ」と仰っていますが、それではもったいないということで、せめてお弟子にさせていただきますと、お釈迦さまの「釈」の字を頂いて仏教の先生より賜る名前なのです。
少し法名についてお話しさせて頂きましたが、お釈迦様は何を教えて下さった方なのか少しでも興味を持って頂ければ幸いです。
今年の冬は暖かいように思います。
気のせいなのかどうなのか。
さてさて、終活。最近ほんとよく聞くようになりました。
終活は残すものに負担をかけない、自分の希望を伝えておける、今後の生きる活力に。
そんな意味合いを込めて行う方が多いようです。
先日ニュースで終活年賀状というものをやっていました。
年賀状の印刷業者「アルファプリントサービス」によると、年賀状の終了宣言をすることを「終活年賀状」というそうで、70歳以上の人を中心に、すでに去年の約5倍の注文が入っていると。
個人的にはこのニュース何か寂しい気持ちになりました。これは終活というよりは、意味合いが変わってきそうな‥。
終活で何かご相談ありましたら、いつでもお待ちしております。
年末が近づき、各地で年末の恒例行事の準備が
始まるなどのニュースをが聞かれる様になりました。
私の地元でも昔は近所の子供が集まって
よく餅つきをしていました。
今でも行われているかはわかりませんが
懐かしく思います。
当社は地域の行事にも積極的に参加しています。
見かけたら気軽に声をかけてください。
今年もあと20日ほどになりました。
毎日、暖房のきいた部屋で仕事をしていると外との外の寒さが分からず、
薄着で出てしまって、失敗したということがあります。
そして、また乾燥に悩まされる日々を過ごしています。
家では、ペーパー加湿器をベッドサイドにおいています。
今のところ、なんとなく効果があるような気がしています。
さて、12月に入ってから歩いている人も早足になっている気がします。
ただ寒いだけなのかもしれませんが。
私たち業務課では毎年、資料を整理したり、来年のために資料を
見直したりするのですが、なんとなく気持ちだけ焦っていて
実は計画通り進んでいないのでは?と思うことがあります。
毎年のことなので、年々スピードアップしていくはず!と思っているのですが。
気を引き締めなければなりません。
皆様、今年やり残していることはないでしょうか。
私は、仕事やプライベートであれもこれもと思い浮かびます。
少しでも減らせるよう努めたいと思います。
ということで、昨日の続きです。
病棟や受け持ちの科などによってもいろいろ違うのでしょうが、まあ看護師さんは勿論、医師の大変さは、こちらがわから見ないとなかなかわからないと思います。
これは、介護関係の方も同様のことでしょう。
いま、医師不足や看護師不足が深刻と言われておりますが、まさにその通りかと。
こういった相手に本来は時間をかけて対応する方がよいような職業に限って、やはり労働環境や労働条件など様々なことから敬遠される若者も多いのかもしれませんが、なにかしら仕事に対しての純粋なモチベーションがないとできない、つまりお金という部分だけでは務まらない仕事かと思います。
いわゆる、「大変な仕事ですね」と言っていただけることがよくある仕事です。
そして、対人というのも、たとえば直接肌に接する機会や当たり前ですが命に関わるという部分では「失敗が許されない」ということも精神的にもきつい仕事ではないでしょうか。
失敗というのは、プロセスでのこと。医療ミスなどが世間で大きく騒がれた時期もあります。
要は、命に関わる、または患者の尊厳に関わる、という中ではいかに信頼が結ばれるかがカギになるわけです。そこに付け焼刃の見せかけの優しさや配慮は却って信頼を損なうリスクがあるわけです。
だからこそ、プロセスが大切で、コミュニケーションが絶対的に重要になると。
ただそこに人員不足などが関わってくると、どんなに高度な検査機器や技術の高い専門医がいたとしても、存分に力を発揮できないという場面も、あってはならないのですが、出てくるケースもあるのかもしれません。
そんな感じで、病院内からいろんな形であちら側目線でみると、実際に自分がどうなのか、自社はどうなのか、いつもお迎えに来たときにどういう対応が故人様始めご遺族や、最終的に病院側の方にも安心していただけるのか?なんてことを考えるきっかけになったことは言うまでもありません。
そんな経験も胸に、他社にはマネのできない「お迎え」で全ての関わる方に安心感を
なかなか日頃、相手様の立場に立ってというのは、気を付けてはいるものの、なかなか上手くいかないことも多々ございます。
とくにご葬儀の場合、ご遺族の立場になって行動やお手伝いをしなければななりませんが、本当にご遺族や故人様の立場になってすべてが行えているか?となると、まだまだ足りないことがたくさんあると反省するのです。
無論、当事者と同様の気持ちになるなんてことは、逆に憚られますが、少しでも相手様の気持ちに、という思いは常に持ち続けなければならないと日々、自分を戒めるわけです。
さて、日頃「お迎え」に病院へ伺う機会はよくございます。
その病院へお迎えにあがりますと、病院の特色などが垣間見られるわけです。
故人様への対応、ご遺族への話し方、お見送り時の言葉遣いや態度などなど。
よく病院は、生きている方のための場所なので、お亡くなりになられた途端対応が・・・なんてことも聞いたりすることが実際にございます。
またどういう訳か、我々葬儀社になぜか冷たい対応をされる看護師の方もいらっしゃいます。
業界が違うと、当然温度差もあるわけですが、どうしても「業界」というくくりで見られることもあります。
これは、私たちも同じで、◯◯病院へお迎えにいったらそこの看護師さんの態度が・・・となると、その◯◯病院はよくない病院だとひとくくりに言われることもあります。
実際は、仕事をされていらっしゃる方がたくさんいて、その一人ひとりは全く別の個であるにも関わらず、です。
そんな私が、たまたま、病院の医師や看護師の仕事ぶりや院内での所作などをじっくりと伺う機会に恵まれ?たのかどうかは置いておきまして、そんな機会がございましたのでご紹介できればと。
つまり、相手様の行動を見て相手様の立場が少しわかったような・・・というお話です。
どんなお話しかは、明日へとさせていただきます。
毎日、寒い日が続いておりますが、参列される方々も風邪をひかぬように、十分、寒さ対策をしてお越し下さい。
やはり「カイロ」が一番役に立つと思います。貼るタイプなら、首元と腰元に貼ると全身が温もりますのでお試しください。
ついこないだ年が明けたような気がします。
一日いちにちが本当に早いものです。
この時期おいしい食べ物といえば鍋ですね。
体の芯から温まる。毎日でもいいかも…。と思ってしまうほどです。
そろそろ大掃除を始める方もおられるのではないでしょうか。
一年のほこりを綺麗にして新しい年を迎える。
今月19日のバザーでは掃除用品も10円で販売します。
沢山の方にご来店いただけますように
ご近所の方に声をかけて大池橋店までおこしください。
スタッフ皆でご来店をお待ちしています。
親が亡くなると親名義の銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫等の口座が凍結されそれ、お金の引き出しや入金ができなくなると聞いたことがある人も居るのではないでしょうか?
実際にありえることなのです。問題はそれがいつ凍結されるかです。
そのタイミングは原則として親族が銀行などの窓口や電話で直接その旨の連絡をした時点です。金融機関の対応としては、一般的にその時点で連絡をした親族に死亡した本人との関係性を尋ね、その情報を本店の相続担当部署に伝達した後に口座が凍結されると言われております。したがって、死亡届を市区町村の役所に提出した時点で口座凍結されることはあまりありませんのでご安心ください。
朝晩は冷えますね。それでも日中は暖かく感じることもしばしば。想定の気温との違いに戸惑う日々です。
さてさて、この時期になると昔は年賀状の準備でばたばたしていたのを思い出します。
今は印刷でさっと終わりますから、まだまだ余裕があるように感じます。
それでも喪中はがきはそろそろ出さなくてはいけませんね。
皆様お忘れではないですか?
かわかみ葬祭でも取り扱っております。
なにかございましたら、いつでもご相談ください。
早いもので今年もあと1か月になりました。つい11月には今年も残り2か月といっていたのに早いなあと思います。12月は旧暦で師走といいます。由来はいくつかあるみたいですが、師(お寺さん)が仏事や読経のため、お家に忙しく走り回る時期だからという説もあるそうです。
もちろん各ご家庭も、お寺様に負けないくらい年末年始は忙しくなってくるかと思います。大掃除から始まり仕事納め、お正月の準備など。お墓にもお参りに行かれる方も多いと思います。新しい一年が気持ちよくむかえられるように、また今年にやり残したことがないように残りの数日を大切に過ごそうと思います。
早いもので、今日から12月。
今年も残り1か月となりました。
1年早いなぁ、と毎年の事ながら思ってしまいます。
何かと浮足だってしまいそうな季節ですが、
あと1か月、気持ちを引き締めて
乗り切ろうと思います。
早いもので、11月も終わりです。 すれ違うご近所の方とのご挨拶も「急に寒くなったねー」になりました。 今年も残り1か月になりましたが、この1年が早く感じていてあまり実感がわきません。 突然ですが、みなさんは、どんなお葬式がしたいですか? 先日見ていたテレビで、ゲストの皆さんにこう質問していました。 色々皆さんご意見が出ていましたが、 さて、私だったらどんなお葬式をしたいかな。 母や親戚からは、何かの話の流れで少し聞いたことはありますが、 自分自身となると何にも考えていません。 最近、引越を考えているので、整理をし始めて改めて、 「これは、ずっとあっても使わないなぁ」と思うものが、たくさん出てきて これも生前整理だなと少し笑ってしまいました。 最近は、終活が話題になり、事前に相談する方も増えてきていて 家族で話題にすることもあると思います。 少し余裕のある時のほうが、いろんな話ができるかもしれませんね。
2019年も残り32日なんですね。。。目まぐるしく進む日々。
12月に入れば、あっという間に新年を迎えてしまう年末の忙しさ。
一日一日、気合を入れて頑張ります。
11月も終盤に入り冬らしい気温になってまいりましたが皆さんしっかりと寒さ対策はされているでしょうか?
年間で見ると初夏が最も少なく、暑い真夏に少し増え、晩秋から年末にかけて一気に上昇。そして寒さの厳しい真冬にピークを迎えるのです。
冬は寒さの影響で、血圧が高くなり、心筋梗塞などの心疾患の危険因子のひとつ。また、寒暖差などによって引き起こされる血圧の急な変動も血管や心臓に負担をかけ、突然死にもつながりかねません。
高齢者の場合、とくに注意したいのは冬の入浴中の心臓発作です。お年寄りが入浴中には、家族が途中で声をかけるなど、気をつけてあげることも大切です。
寒い日は長湯すると気持ち良いと思いますが特に高齢の方がお家にいらっしゃる場合は、冬だから長湯しているのだと決めつけずに、声を掛けて差し上げるようにするといいかもしれませんね。お身体に気をつけて冬を乗り切っていただければ幸いです。
先日バイキングに行ってきました。
最近はブッフェ形式のお店があちらこちらにあります
各お店ごとにいろんな工夫を凝らしておられます。
ラーメンがあるかと思ったら日本食、中華、台湾など
いろんな料理がところせましと置かれている。
少しずつとって食べると本当に幸せを感じるものです。
空間と味、それに視覚などいろんな工夫がされていました。
葬儀もまた上記の料理屋さんと同じくその空間に見える視覚、
音楽の聴覚、それらすべてが揃ってよい葬儀になるわけです。
私どもは空間にこだわり、すべてのお客様に良い葬儀を提供できるように
これからも考え続けて参ります。