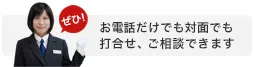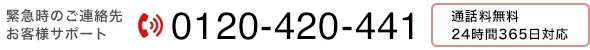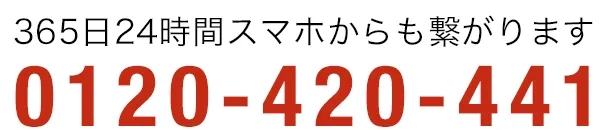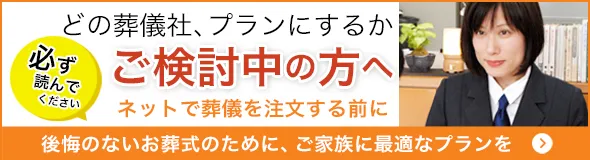ご葬儀の際、当然ながら故人様のお顔を見るものであると思われている方も多いのではないでしょうか。
ご自宅や葬儀の式場で故人様のお顔を拝し、故人様の最期のご様子を話し、偲ばれるわけです。
そうすることで、本当に亡くなられたのだな、という実感や生前の想い出が溢れ出てくるものなのだろうと思います。
しかし実際の現場に携わらせていただいていますと、ご遺族から、故人様の最後の姿を見せたくないとおっしゃられることや、または故人様が生前に「身内にはまだしも友人には見られたくない」と言っていた、などのケースもございます。
たとえば、闘病の末にやつれた顔は、ご親族もそして故人様ご自身も見られたくないと考えられることはよくありますし、一人暮らしで、ご自宅で亡くなってから長い時間が経ってしまったケースなどでは、身内であってもあまり見せたくはないお姿かと思います。
私どもの提供しているサービスに湯灌やエンバーミングというものがございます。
最近では湯灌やエンバーミングも一般的に広まっており、処置を施すことで、生前のお元気なころのイメージに近いお姿にして差し上げることもできるほど技術も進歩しております。
ですから湯灌に立ち会いされたご遺族からはよく、「最後にお化粧をしてあげられてよかった」とのお言葉をいただいたり、立会することができなかったご遺族も式場で再会した時に「こんなにも奇麗になって」と感動されたりする方も多くいらっしゃいます。
これは本当に現場担当者としても救われる思いになります。
しかし、様々な技術をもってしても、どうしても最期にご拝顔することが難しいこともあります。
特に亡くなってから長い時間が経ってしまった場合は、生前の面影が全く無くなってしまわれている、ご拝顔されないほうが良いと思うことも正直ございます。
しかし、ご遺族にしてみれば「それでも・・・」と思われることは当然のことです。
故人様に近しいご親族に「故人の尊厳」について説明をさせていただくというのは、この仕事に携わらせていただいていても、憚られます。
そして、憚りながら説明をいたしたとしても、私たちが決められるようなことではありません。
どのような状態であっても、故人様の面影を追い、それを感じられるのがご遺族なのだと思います。
人の最期はさまざまな表情をされております。穏やかな表情で最期を迎える方もいらっしゃれば、私たちから見て面影がない方もいらっしゃいます。
どんな技術をもってしても、やはりご納得いただけない場合もあるのではないでしょうか。
それは技術に対してではなく、故人様に対する思いに。
生前にいつも傍らでお世話をしたり、常に顔を合わせていたり、最期の最期までそういうことができれば、そのような複雑な思いにはなられないかもしれません。しかし、現実問題としてすべての方が、お亡くなりになられる直前まで傍にいられるわけではありません。
そこに、ご遺族の気持ちの中に何かしらの「罪悪感」が芽生えていらっしゃるように感じられます。
私は、様々な故人様にお会いし、時にはご遺族だからこそご拝顔されないほうが良いというケースにも立ち会わさせていただいたこともございます。
そのときに私が常に心がけているのは、「もしかしたら私が最期にご拝顔させていただいているのだ」という気持ちと、その表情を何かしらお伝えすることが私の使命ではないか、と思うようにしています。
それはまだ私が入社して間もないころこんなことがありました。
大変な事故であったため、正直ご拝顔などは全く難しいような状態で若い息子様を亡くされたお父様から、「息子はどんな表情だった?」と尋ねられたことがございます。
そのとき意を決して、私はありのままをお伝えしました。
もしかしたらお悲しみを深くさせてしまうかもしれない、泣き崩れてしまわれるかもしれない、そんな思いが私の中で駆け巡っていたことを今でも鮮明に覚えています。
しかし、お伝えした後にお父様がおっしゃられた言葉こそ、もしかしたらご遺族が本当に求めていらっしゃることではないか、と。
「本当にちゃんと息子の様子を見てくれたんだ。嫌な仕事をさせたね、すまなかったね、ありがとう。よくわかったよ。そんなんになっちゃったか・・・でも正直に話してくれてよかったよ、ありがとう」
このとき、私がどんな仕事に携わっていて、どんな重要な役目であるのか、そして美辞麗句を並べたり、言葉でご遺族を癒すことを考えたりすることの浅はかさを痛いほど知りました。
湯灌やエンバーミングの技術、式場の環境、そして当たり障りのない声掛けで、ご遺族が癒されるわけがない、と。
この思いが、私の葬儀社スタッフとしての気持ちの根幹にあることは間違いなく、ご遺族がご拝顔をされたくてもできないような場面に遭遇した時、私には最期の表情やご様子をお伝えする重要な役割があるのだ、という思いで必ずご拝顔させていただこうという固い決意を持たせてくれた何にも換えられない貴重な現場体験でした。