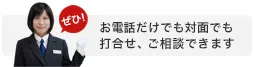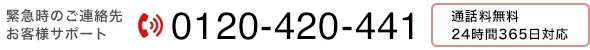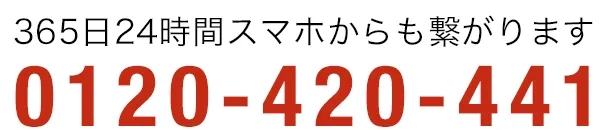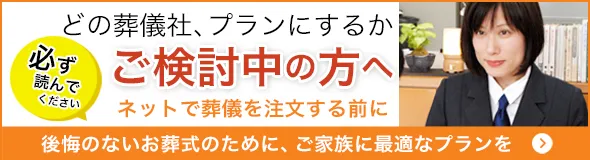「死ぬ」という言葉は忌み言葉として、「なくなる」「身まかる」「お目出たくなる」な
どと言い換えられたりします。恐らく「死」について、言葉にすることすら躊躇わられる
というその感情が、このような言い換え表現をいくつも生み出したのでしょう。
「死」にまつわるものに可能な限り関わりたくないと思うのは人情であろうと思います。
いつかは自らの身にもおとずれるとわかってはいても、出来うる限りそれには目を瞑り
たい……。だから、「死」を極力目にすることがない世界というのは、ある意味で人の目指
した理想の世界であるのかもしれません。
1000年以上も前の話になりますが、平安時代には300年以上の長きに亘って死刑の執行
が停止されていた時代があります。これには、死刑のない素晴らしい時代であったという
評価もありますが、その動機は博愛的なものであるよりも時の貴族たちによる極度の「死」
に対する忌避の感情であったようで、そのような感情が結果的に後の武士の擡頭を許した
などとも言われています。
そして私たちの生きる現代は、再びそのように「死」を忌み嫌う時代であるように思わ
れます。
多くの方が病院で亡くなられ、そしてそこにある、それがそれとは覚られないようにと
てもよく配慮された霊安室の存在は、あるいはその象徴であるのかもしれません。
しかし「死」は誰にでも平等に訪れるし、特段変わった出来事でもありません。緑ナン
バーをつけた寝台車は街中を忙しなく疾走していますし、葬儀の開催を告げる矢印看板も
そこココで目にします。少し目を凝らせば、日常の中でもその断片を見つけることは容易なのです。
納棺の前に行う旅装束へのお着替えは、ご遺族の方々にも手伝って頂く、とても緊迫し
また充実した時間です。白装束、足袋、脚絆、手甲、草鞋と着替えが進行していくその中
で、ご遺族様の緊張は徐々に安堵へと変化していきます。それはあるいは人が、(愛する)
人の死を受け容れる縮図であるのかもしれません。
「死」と正面から向き合うことは、生を充実させるために欠かせないことであろうと思
います。
とはいえ私自身も、当事者になった時にたやすくその「死」を、理屈どおり受容できる
とは思いません。そこへの距離感や付き合い方は、日々の意識や行動の中ですこしずつ錬
磨するよりほかなく、そのように努めていきたく思いつつ、日々の業務に努めております。