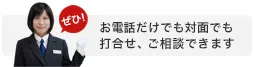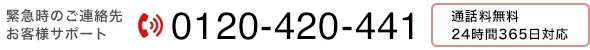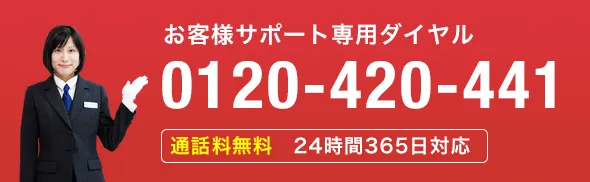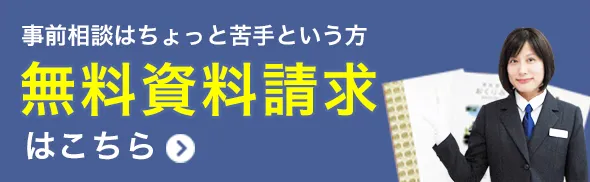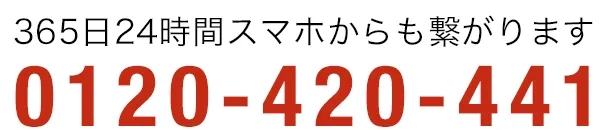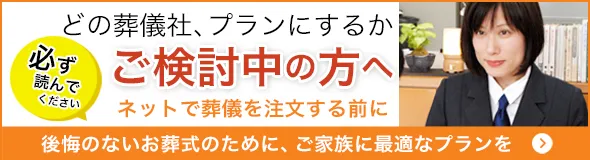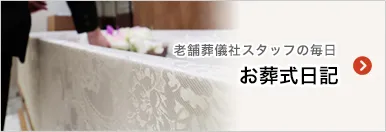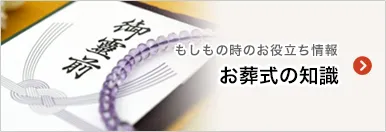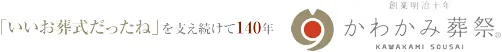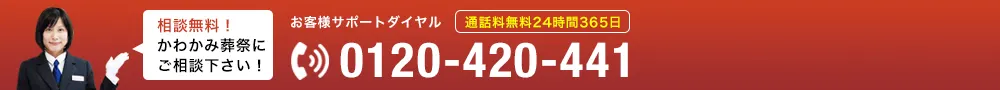小説
をあまり読む方ではないのですが、何かしらきっかけがあれば、いわゆるジャンル的には文学小説は読むことはあります。
西洋ものですと、いわゆる翻訳版しか読めないわけで、原文まま読めたらさぞかしまた内容の捉え方もちがうのであろうな、 と思いながら読み進めるわけです。
言葉の捉え方、同じ言葉でもニュアンスの違いや、翻訳者の感覚などが、翻訳版の面白いところなんでしょうが、文化の違いで多少翻訳では、表しきれないことなんかもあるんだろうな、と。そして読み手の私のリテラシーの問題も無論あるわけで。
作者が意図した、言葉の1つひとつがうまく読み込めているのか、感情的な表現をきちんと感情的に捉えられているのか、と考えながら読み進めていく。(日本文学が読み込めているわけでもないでしょうが)
文学や文章も、絵画など芸術作品と同じように捉え方の違いで、読み手の解釈や評価も変わってくるのは当たり前で。
多様性が叫ばれ、次に多様性は否定され、そして今となっては多様性って結局なんなんだ?となっている気がしますが、多様性を「すべて認める」的なとらえ方が横行し過ぎたようにも思えるわけで。
すべて認めると、多様性は逆になくなるのではないか?という思いに駆られます。
もうあまり長々と語るような内容ではないので、この辺にしておきますが、
混沌から秩序が生まれるように、多様性を良い意味で最大限に活かすためには、普遍的真理はあると思っている私は、その普遍的真理の上に成り立つものだと考えているので、そこがズレると多様性を認めるのは、ただカオスを招くだけです。
性格や意見の不一致まで、多様性の範疇にしたりすると、もはや社会活動は機能しなくなるような気がしております。
実は、こういうことが身近に発生しているようにも思い、受け入れる側の度量にかかっているようにも思うわけで。
HO