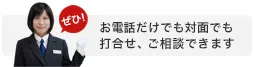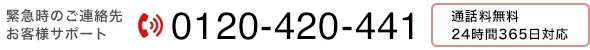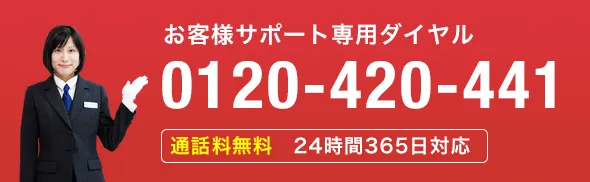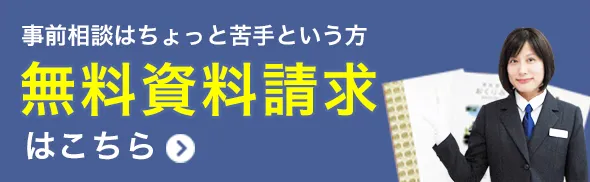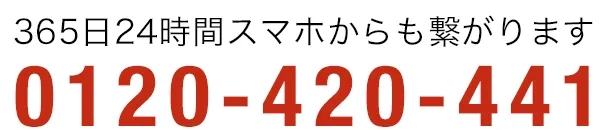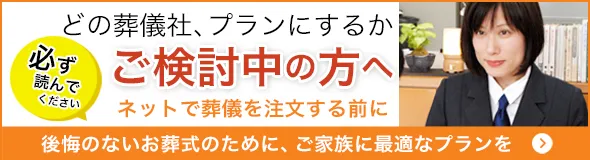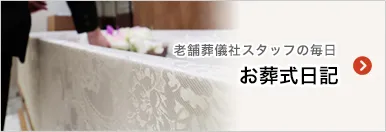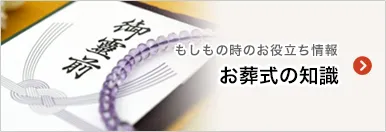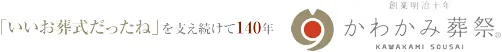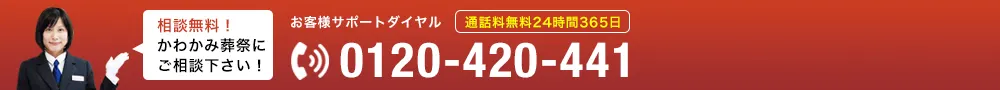YouTubeとお葬式~SNSがつなぐ、命と向き合うきっかけづくり~
最近、社内で運営しているYouTubeチャンネルの再生データを見ていて、ある傾向に気づきました。
「家族葬」「一日葬」「直葬」「安い葬儀」など、簡素化された葬儀スタイルに関する動画がよく見られている一方で、「葬儀マナー」「香典の書き方」「法要の流れ」など、しきたりや作法に関する動画も根強い人気があります。
宗教離れ、少子化、核家族化が進む中で、「葬儀はもっと簡単に」「負担なく済ませたい」という声が増えているのは事実です。
しかしその一方で、「最低限のマナーは知っておきたい」「親の代から受け継いできたことを、失礼なく守りたい」といった気持ちも、動画の再生数から垣間見えます。
現場のスタッフからのちょっとした会話の中から、こうした“揺れ”を日々感じます。
「宗教は関係ないけれど、やっぱりお坊さんには来てほしい」
「家族だけで静かに送りたいけれど、近所の方にも失礼がないようにしたい」
「費用は抑えたいけれど、心は込めたい」
そんな想いが、葬儀の場には確かに存在しています。
SNSやYouTubeは、そうした“迷い”や“戸惑い”にそっと寄り添うツールになり得るのではないか。
動画を通じて、誰にも聞けなかったことを知り、
コメント欄で誰かの体験に共感し、
「自分も、ちゃんと向き合ってみよう」と思えるきっかけになる。
それは、葬儀社が情報発信をする意味でも、非常に大きな価値だと感じています。
SNSというのは、使い方を間違えると、どんどん負の方向へ進んでしまうという危険性を多くはらんでいることは、皆さんもご承知の通りかと思います。
それはAIを使っていくうえでも同様のこと。結局、さまざなSNSやコンテンツはAIが見ている人を、見続けさせる、迷わないように考えさせないようにするシステムがAIによって選別されているような現状です。
AIがこれから世の中でスタンダードになることはもはや止められないわけで、そうなるとAIが生成したものを、正しく評価できるかどうかということが、人の大切な能力になってくるはずです。
だからこそ、特に人の生死など、倫理的なことへの学習は、小さいころからの大切な学習として位置付けて欲しいと強く思っています。
それは、先日リアルな場で、子供たちにお棺に絵を描いてもらうという、ちょっとしたイベントを行ったときに、ふっと感じました。
「死」を連想させることを子供に触れさせたくない、大勢のいる場所でそういう行為は、適当ではないという親御さんもいらっしゃいます。それは私も子を持つ親として、心配為される気持ちは理解しないでもありません。
ただ、ゲームの世界では疑似とはいえ、人を傷つける行為は行われており、少し大きなお子さんであれば、慣れ親しんでいるくらいです。
結局、自分で手を下しているのかいないのか、が問題視されているように思います。
私自身、葬儀の仕事に携わるようになってから、「死」とは何か、「命」とは何かを、歳を重ねるごとに深く考えるようになりました。
そして思うのです。
子どもの頃から「死」を遠ざけるのではなく、
「死」を知ることで「命の大切さ」を感じられるような社会であってほしいと。
葬儀は、誰かを失う悲しみの場であると同時に、
命の尊さを知る学びの場でもあります。
その入り口が、YouTubeやSNSであってもいい。
むしろ、そうした身近なメディアだからこそ、
これまで届かなかった人たちに、葬儀の意味が伝わるのではないかと思うのです。
これからも、現場での気づきやお客様の声を大切にしながら、
SNSを通じて「新しい葬儀のカタチ」を模索していきたいと思います。
それは、形式や費用の話だけではなく、
「命と向き合う時間」をどうつくるかという、
とても人間らしい問いへの挑戦なのかもしれません。