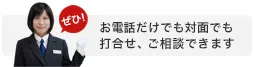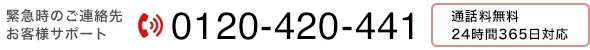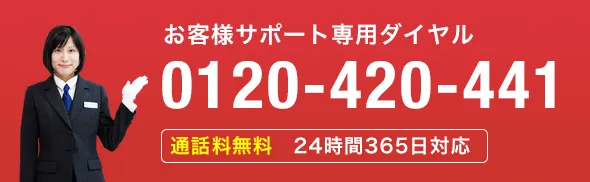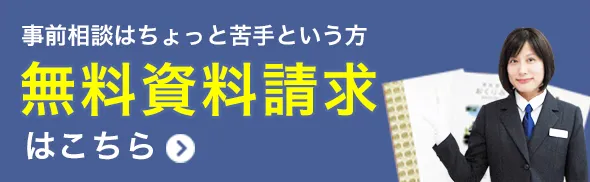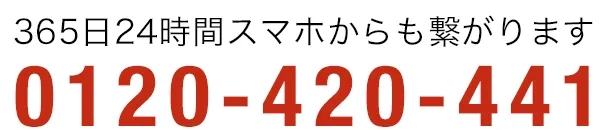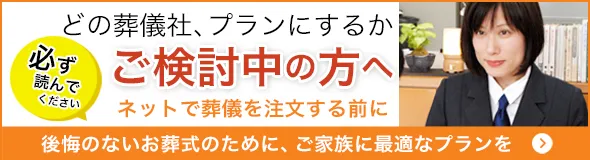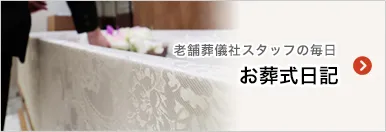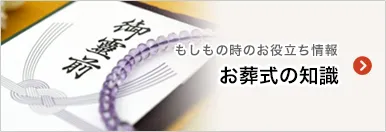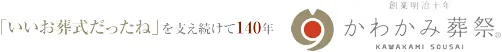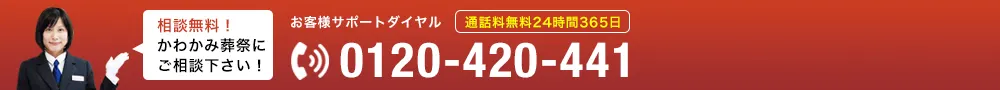事前相談
なかなか、葬儀の相談はしにくいものですが、お気軽にご相談ください。
買い物のついでや、お散歩のついでに立ち寄られてパンフレットを持ち帰えられる方も大勢おいでですよ。
遺骨は菩提寺や霊園にあるお墓に埋葬して供養するものだと考えている人が多くいらっしゃることだと思います。
近年では、お墓の形にこだわらない方も増えて来ております。
その中でも自宅供養される方もいらっしゃいます。墓埋法では、遺骨を勝手に庭などの土の中に埋めることは禁じられています。しかし、遺骨を手元に置いておくことは問題ありません。また、遺骨をいつまでにお墓に納骨しなければならないという決まりもないのです。
様々な理由で自宅供養を選択される方がいらっしゃいます。どのようにすれば良いかと悩まれるならば、一度ご連絡頂ければ幸いです。
6月11日は、雑節の一つ「入梅」になることが多いことから傘の日と言われるそうです。梅雨入りしている地域も多くなってきました。傘といえば、どこかに立てかけて忘れるということを何回かしたことがあるので、今年は買い替えなくていいようにすることが梅雨時の目標だったりします。念のため、傘を持たれている方も多いと思いますが、降っていなかったら電車や職場、お店などに忘れてしまいがちなので、お気を付け下さい。
先日、たまたまお墓の近くを通りました。綺麗なお花がそなえられていたので、最近お墓詣りに来られたのかな~と思って見ていたのですが、お供えされているものに生のお米はありませんでした。もしかすると、すでに鳥達に食べられてしまったのかもしれませんが、少し調べると生米をお供えするのは地域によるとのこと。実家ではそれが普通だと思っていたことも、実は違うことがたくさんあります。今度、実家に帰ったらお供えする理由を聞いてみようと思います。
今日の夕方、私は仕事中でしたが普段は滅多にメールなど送ってこない息子からメールが届きました。
少し嫌な予感がしたのでメールを確認した所…飼っていた金魚が動かないとの内容でした。
昨日の夜から様子が変だなとは思っていたのですが、やはり寿命が来てしまったようです。
町のイベントの金魚すくいで新しく家族になっておよそ3ヶ月の短い付き合いでしたが、そのメールを見た瞬間は頭が働かなくなり明らかに思考が正常ではなくなりました。
これが肉親だったらどうなったのか…想像もつきません。
そんな状態だからこそ我々はより冷静にご逝去のご連絡をお受けしております。
気が動転して正常な判断ができない状態でも一つ一つ確実にお伺いいたします。もしその瞬間が訪れてもどうか安心してご連絡下さい。
梅雨の季節となり食中毒のニュースも聞くようになりました。気をつけないといけない事がまたひとつ増えてしまいます。いろいろなウイルスと共存している以上、自己管理するしか仕方ないですね。
神戸のとあるお寺では、2年ほど前からユーチューブで法話を配信されているそうです。檀家さんのお寺離れもあってでしょうか、お寺の行事や、中学生の生徒さんとの共同制作も配信されていて、反響も大きいようです。病気や高齢のためにお寺に行けない方々にも好評で、中には「自殺しようと思ったが、動画を見て思いとどまった」という内容のお手紙も寄せられているとか。
そのお寺で先日「H1法話グランプリ」が開催されました。聞きなれないグランプリですが、宗派も関係なく、全国各地から集まった僧侶7組8人が、それぞれ制限時間10分で法話をします。5人の審査員の他に約450人の来場者が「もう一度会いたいお坊さん」を基準に投票し、今回は兵庫県丹波篠山市のお寺のご住職がグランプリに輝いたようです。
お寺様のお話は長いものもありますが、制限時間10分というのがちょうどいいのかもしれませんね。まだホームページでその時の模様を見ることができるので、是非見てみようと思います。
先日こんなニュースがありました。
殺虫剤と蚊の話です。
殺虫剤は蚊を減らすのに失敗しているどころか、天敵を殺してしまうことによって、むしろ蚊を繁栄させているかもしれない。
蚊には耐性ができていて、天敵のイトトンボの幼虫には耐性ができなかったためのようです。
こうしようと思っても結果が全く違うことになっていたと。
ここまで地球規模の話は難しいですが、身近なところにもそんなことありますよね。
よかれと思ってやったが、違った方向にと。
お葬式にもあるかもしれません。良かれと思ったら宗教的にはNGだったと。
難しいですよね。
いつでもご相談ください。
今日は天気予報どうりの大雨でとなりました。
関東の方ではまもなく梅雨入りするそうです。
気温が上がらないので雨もいいものですが、
外出するのは面倒になってしまいます。
出勤時や帰宅時、あちこちでアジサイの花が咲いているのを
みかけます。
アジサイは土壌によって花の色が変わると聞きました
まだ咲いていないアジサイが何色の花を咲かすのか
今からたのしみです。
経済の循環、いわゆるサイクルを考えてみると、好景気と不景気が波の大きさ、期間の差こそあれ、常に繰り返しています。また、景気が上向き、または下向きに動いているその道中でも好と不が短く繰り返されています。
人間のバイオリズムも同じように好、不調を繰り返すなかで、いかに好を長く維持し、不調を最小限にし、ダメージを食い止めるか、がポイントです。
気の波をうまくコントロールできると、派手ではないけれども、安定感のある波動が形成されるのでしょうか。
質実剛健の、質とは素朴、つまり質素という意味合いがあります。
勝手な解釈でいえば、質=クオリティーとしても、素が大切であり、素の状態が高いレベルであると、派手ではなく真の意味合いでのハイクオリティーが実現できるのではないかと思うのです。
葬儀においての、ハイクオリティーなサービスとはまさにそういうものではないのか、と考えており、葬儀社は精神的な部分で質実剛健でなければならないのではないか、と。
様々な志向を凝らしたサービス、意味や意義が浅いサービスなどをみると、気を引き締めると同時に、お客様にとって質実剛健な会社であり社員でありたいと思います。
今日も良い天気ですが、週末は雨の予報ですね。そろそろ雨の多い季節に
なってきました。引越をしようかと思っているのですが、当日に雨が降っていたら
イヤだなと先延ばしにしています。
といっても、まだ引越先を決めていないのですが。
さて、伯父の家にお寺様が来られる日と、私のお休みの日がちょうど重なったので
行ってきました。
いつもいろいろなお話をしていただいて、気づけば1時間くらい経っていることも
あります。
世間話からご家族のこと、お仏壇のお手入れのこと等々本当に幅広く
そして、楽しくお話をいたします。
ですので、伯父も伯母も「聞いていいかな?と思うようなちょっとしたことでも質問しやすいわ!」といつも言っています。
私たちもお葬式に関することでちょっとしたことをお聞きになりたい方々から
「川上さんとこやったら、聞きやすいわ!」といつも言っていただけるようにと
思いながら、お仕事をさせていただいています。
6月に入りました。
早いもので今年も半年を向かえました。
そろそろ梅雨の時期を迎えようとしています。
雨ばかりは嫌ですがこの時期がないと実らないものも沢山あるので
必要だとは思うのですが…。
この季節私たちも突然の雨に気を使いながら葬儀の準備を行っています。
出棺の際に雨が降る場合の対応、通夜の際に急に雨が降ってきたときの対応など
人が集まる場所ですので細心の気配りが出来るように日々努力を行っています。
なかなかいつも100%とは行かないまでも少しでも自然の現象にも対応できるようにと考えています。
今までも、そしてこれからも品質の向上を考えて行動をして参ります。
最近では、独居のまま亡くなる人が増えており、後に大量の家財道具が残されることが少なくないそうです。
賃貸住宅の場合は、早急に部屋を引き払う必要もあるため、遺品整理専用の業者などにお願いするということも増えているようです。
中には不法投棄を行うなど心ない業者も存在すると言われていますので、信頼のおける業者を探す必要があります。
粗大ゴミとして捨てるのはしのびないと思われる品々もあるかと思います。その場合、お焚き上げという選択肢もございます。有料になりますが、お寺様にご供養いただき焼却くださいます。わからない事などあればご気軽にご相談いただければと思います。

なんとも、耳の痛い言葉が並んでいます。この言葉を噛みしめて今日も頑張ります。
先週の日曜日に息子の小学校で運動会がありました。数年前から夏の暑い時期の練習での熱中症予防の為に5月に運動会をするようになりました。
…が、新学年になって一ヶ月足らず、練習期間も短くそして子供達もどこか完全には打ち解け合っていないような雰囲気も。
特に六年生の組体操は練習不足感は否めませんでした。
やはり運動会もしっかりと練習をして準備をして、先生とも児童同士でも話し合ってお互いに理解し、信頼して…その上で良いものができるんだと思います。
ご葬儀も一緒です。
しっかりとお話しして理解して、準備して、いいご葬儀ができるように…
まずはお気軽にご相談してみてください。
我々はいつでもお待ちしております。
今日は5月最後の日です。新しい元号になって早1か月たちました。もう間違って平成と書くこともなくなりました。来月には平成がもう懐かしくなっているような気がします。そうやって一か月、12か月、1年、10年、20年と経っていくんだな~と思いました。
最近テレビでお墓まいりのことをしていました。ある地域では 親戚や家族が集まり、お墓の掃除とお墓参りをします。 これだけだと普通のお墓まいりですが、そこはお墓参りの後は、ご先祖様のお墓の前に、ビニールシートをひいて、ピクニックのようにご馳走などを食べて皆で楽しむそうです。なので、お墓の前は広いスペースがちゃんとあるようです。先祖の供養をするという意味のほかに、親戚が集まって、近況報告をする場としても大事な行事といわれています。供養の仕方の地域性も興味深いなと思いました。
暑くなりました。これからもっと暑くなるかと思うとゾッとしますね。
夏バテ、熱中症対策早めにしていきましょう。
LGBTの方々のお墓に対するニュースがありましたので少し紹介してみたいと思います。
「日本の場合、お墓は血縁関係のある家族で入るもの、とされています。法律的には血縁関係がなくても問題ないのですが、それ以前のハードルが高いんです。たとえば霊園や寺院などの運営側の規定、お墓の名義人の問題、親族の同意、永代供養のための墓守(=子孫)の存在など、さまざまなハードルによってお墓を持つことは難しいという現実があるんです。生涯結婚しない方もいるし、子供がいない方も、LGBTQの方もいる。家族形態が変化している現代において、お墓のあり方も変わっていくべきなのではないかと実感しました」と加登さんは語る。
そしてついにこの8 月、加登さんはこのハードルをクリアした。別姓の事実婚夫婦や同性カップル、友人同士、実の兄弟、親子、養子縁組など、血縁関係の有無を問わず、ペア(2人組)であればどんなカップルでも一緒にお墓に入ることができる「永代供養ペア墓 よりそい」を、兵庫県川西市にある川西中央霊園に開設した。
何気なくニュース見てましたが、確かに様々な考え方がある中で、最後の最後お墓に一緒に入れないでは寂しいですし、変わっていくべきものなのでしょう。
恥ずかしながら私は気にもできていなかった。LGBTQのQが増えていることも知らなかった。さらに少し調べてみるとLGBTQIA+になっていると。
もっともっと勉強しなくてはいけません。
皆様も興味があれば調べてみてください。
何か質問あればなんでもご相談ください。
昨日の雨のおかげで、今朝は暑さも和らぎ
久々に朝の爽やかさを感じることができました。
今年の夏は暑くなる様で、すでに熱中症で倒れた方も
おられるそうです。
最近はホールでの葬儀が増えましたが、まだ地域の会館など
外での葬儀もしています。
いつも以上にお茶を配るなど、熱中症対策を心がけようと
思います。
真夏のような暑い日が続いておりましたが、本日は雨となり、気温は少し下がったようです。湿気でも熱中症になるようですので、水分補給や睡眠の確保など、しばらくはどんなお天気でも気が抜けないようです。
令和を迎えた5月に弊社でも新たな期を迎え、先日全体会議がございました。新しい目標や新しい担当。何事においてもお客様によりよいサービスができますよう、今できる事を精一杯させていただきたいと思います。改めましてよろしくお願いいたします。
毎日夏のような暑さですが、今年の夏はどんだけ暑いんだろうと
思うとため息がでます。
先日、アメリカで働いている従妹が休暇を使って
日本に帰ってきていました。
半月くらいのお休みをもらったらしいのです。また秋には、帰ってくるらしい。
うらやましいなぁと思いながら、色々と話を聞いていると、これからの自分の将来のことを
よく考えていて感心しました。
特に、お金のことはきちんと計画をたてていて、いつの間にこんなしっかりした子になったのかと驚いています。
さて、私たちかわかみ葬祭は、
お客様のご要望をきちんとお伺いし、大切な方のお見送りを
お手伝いさせていただいております。
いざという時に、慌てずに様々なことを決めていただくために私たちがいます。
なかなか家族でお葬式のお話をしづらいものです。
我が家の場合、
テレビを見ながらとか、何気ない会話をしているとき、
まれに母が好きな花で飾ってほしいとか、家族だけでいいけど
○○さんは来てほしいわねとか言ったりすることがあります。
うっかり聞き逃しそうになります。
今は憶えていても、いざその瞬間には、すっかり忘れてしまっているかもしれませんね。
私たちは、全力で皆様のお手伝いをいたします。
お葬式の前のご相談から、お葬式の後のフォローまで
なんでもお気軽にお声かけくださいませ。
異例の暑さ。確かに私が小さい頃、衣替えのシーズンは、6月から。
ただ最近は、5月も半ばになると、もう学生服も冬用なんて着ていられない状況。
そして今年は。もう真夏日ということです。
衣替えのシーズン、これも昔ばなしなのか、それとも我が家だけなのか、タンスや押し入れをひっくり返し、衣服を入れ替えたり、洗濯したり、そんな当時は、面倒くさく思えた光景は(とはいえ、自分は何をするわけでもなかったのですが)、大層なことはないようです。
この時期にはこんなことが、衣替えもそうですし、年末の大掃除なんかもそう。幼い頃はちょっと面倒だなあ、と思っていた記憶も懐かしさに、かわってきた気がしています。
そんな自宅や住まいにある思い出、いろんな思い出を、ひっくるめて大事にされている方も多いと思われます。
葬儀の世界では、最近病院でお亡くなりになられてから、ご自宅にお帰りになられない方もたくさんいらっしゃるようです。
様々なご事情から、諦められるかたが多いのも事実。
特に、うちは無理だと決めつけてしまわれていらっしゃる場合も。
大抵は無理なんてことはないように思います。色々な対策もあります。
ですから、決めつけず必ずご希望のある場合は、相談してほしいです。
本日、ご自宅は無理だ、と思われていたお家に、故人様を連れて帰ることができ、そのときのご遺族の表情を見て、やっぱり我が家が一番だと思われる方には、なんとしても帰っていただきたいと強く思う、そんな暑い日でした。
エンバーミングは、欧米では葬儀葬送に際して一般的に行われています。その目的は、遺族の、かけがえのない人を失った悲嘆を少しでも和らげ、慰めることにあります。
具体的には、まず遺体内に残る飲食物の残滓や体液、血液を吸引して除去したり、動脈から防腐剤を注入するなどの処置によって遺体が常温でも保存されるようにします。さらに、そうした防腐処置を施した後に、遺体の全身と毛髪を洗浄し、美容的な処置や化粧などで表情を整え、仕上げに遺族の希望に沿った衣装を着せます。
こうして、遺族にとっては故人があたかも生前のままに眠っているかのような、安らかな姿に遺体を修復して保ちます。
しかし、費用面でのデメリットもあります。また、欧米では土葬が主流のようでエンバーミングのメリットが大きいですが、日本では比較的早く火葬しますのでエンバーミングのメリットを活かしにくいと思います。
皆さまは、メリットとデメリットをしっかりわかった上でエンバーミングをするかどうかを考えて頂ければと思います。