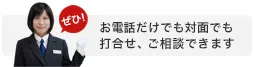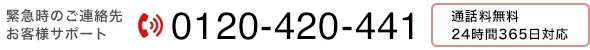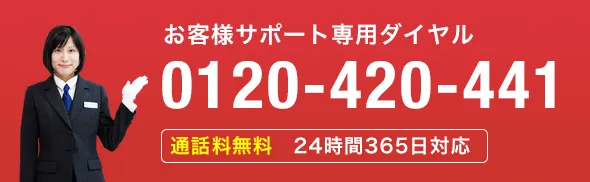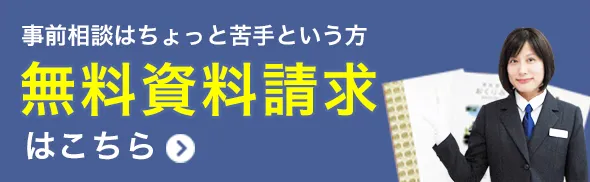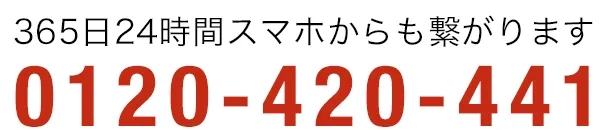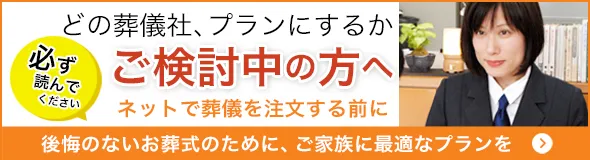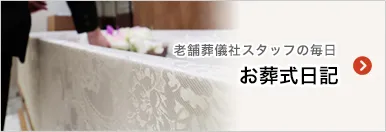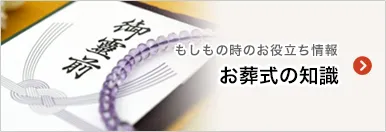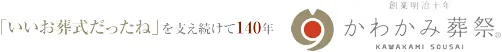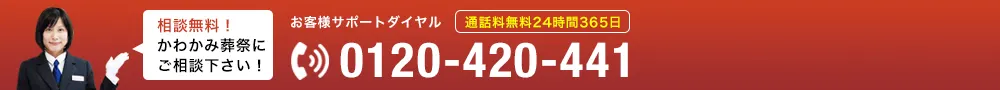四角四面
日々考えることがあります。人間は本来、真面目な動物なのか、
それとも怠惰なほうが勝る動物なのか。
楽することを考えることが本能、本性で、真面目というのは
逆に理性が働くから、ということなんでしょうか。
人間は理性の動物、本能のままに動くのではなく、社会での
コミュニティを形成し、同調したり協調することができる
ことこそ人間の特徴であるわけです。
あの人は、真面目な人だ。
しかし、四角四面になんでも事を運ぼうとすると、
頑固、堅物、真面目というより融通がきかない、となる。
自己中心的だとも。
杓子定規な考え方しかできないといわれ、果ては協調性がないと。
しかし、その逆をいく人は、不真面目、筋が通っていない、わがまま、
子供みたい、そしてこれまた、協調性がないと。
そうなると、協調性というのは誰が柱になるかで良い方向にも
悪い方向にもなるわけです。
四角四面、杓子定規の対義語が融通無礙です。
ご葬儀もおなじく、いろんなスタイルがある現在ですから、
トレンドばかりに目を向けなくてもよいとおもいます。
なぜなら、お葬式はトレンドにのっからないといけないものでは
ないと思うからです。
トレンドではなく、後悔しないことが第一です。
ですから、どうするのが良いのか迷われたら、いつでもご相談ください。
様々な可能性と展開を考えて、融通無礙に対応できるよう、準備しております。
先日、母が以前住んでいた家のお隣さんと
偶然道でお会いしました。
私は全く気付いていなかったのですが、
「げんき?」と声をかけてくださって、たったそれだけでも
なんだか嬉しいですね。
弊社でも毎朝、事務所周辺を清掃していましたら、
お声をかけてくださいます。
私たちも、スタッフ同士で声をかけ合うことはとても大切です。
作業が滞りなくすすんだり、
お客様に同じことをお聞きしてしまうという事もなくなります。
これから、新しい仲間が増えます。
今と同じように声をかけ合えるようにサポートしてゆきたいと
思います。
室町時代―。
僧家において壁に仏画を掛け、その前に押板を置き、その上に花と燭台と香炉を飾り、礼拝をしていました。その押板を床といい、それが次第に変化して作りつけになったものが床の間のもとの姿でした。
つまり床の間はお仏壇の遺風であるといわれています。
床の間が物置代わりや埃が溜まっていませんか?
本来は仏様がおられるところです。
昨日に引き続き七夕の話題ですが、織姫様と彦星様のお話は皆さんご存知の通りです。短冊に願いを書いて昔は良くお願いしたことを思い出しました。
七夕を過ぎますと本格的な夏到来です。
七夕には深い意味があるわけですが、
葬儀にも深い意義がある訳です。
一生に一度のセレモニーをあの世とこの世の架け橋となれるように努めさせていただいております。
日差しが日に日に強くなり、
毎日暑い日が続いています。
明日は七夕ですね。
商店街などで、短冊を置いて
いたりしますが、
いざ願い事を書こうと思っても
なかなか思い浮かばないものです。
七夕に花火大会、夏祭り、
これからの時期、イベントが
各地で開催されています。
私達も地域のイベントには積極的に参加しています。
見かけたら、お気軽に声をかけてください。
七年前にご葬儀を担当させていただいたお客様より連絡をいただき、事前相談をしてまいりました。
前回はお母さま、今回はお父様について。
七年経っても、私のことを覚えておられ指名というかたちでのご相談させていただきました。
前回同様、気さくに接していただき安心した半面、身の引き締まる思いでした。
リピーター様特有の緊張感。今回もしっかりと務めていきたいと思います。
とんでもない蒸し暑さ。昔から台風が近づくと、
大阪は恐ろしく蒸し暑くなる、という話そのままです。
以前はそんなに感じなかったのですが、冷房と蒸し暑さ
の差が、結構体にこたえます。
はー、そんな年齢になったか。と。
当然友人も同じ年齢層。ひさしぶりに大学時代の友人と
連絡をとりますと、話題もそんな健康の話に及びます。
そうなると、どうしても私の仕事柄、飛び越えて
お葬式の話になります。
普段は考えないことなので、みんな実は気になっているんだな
と、思うわけです。
そういえば、以前の仕事でも、若い学生さんのうちに仕事の内容を
啓蒙する活動をしている企業もたくさんありました。
変におもう方もいらっしゃるかもしれませんが、お葬式も
人生設計をしていくうえでは、大事なことかともおもうのです。
早いうちから、意識をしていくのもよいのかもしれません。
そうすると、自分の宗教観や死生観などもあらためてみつめる
きっかけになるかと。
剣道や柔道など武道の道を極める場所が道場のイメージですね。
実は道場は本来お釈迦さまが悟りを開いた場所を意味します。仏教では「道」は悟りのことです。お釈迦さまが悟りを得た「場」ということで道場なのです。つまりブッダガヤの菩提樹下の金剛座が道場なのです。
それがやがて場所はどこでも「悟りを開く場所」が道場になり、さらに一般に「修行をする場所」が道場となっていきました。
初期の浄土真宗では信者が集まって念仏を称えるところを「念仏道場」と呼んでいました。
道場へ通う時は技術だけではなく精神をも修養していきたいものです。
体調の管理が難しい日が続いております。風邪などひかないように気をつけたいものです。
私は最近身体の体調を整えるために、
ストレッチ体操を始めました。
(少しお腹が出てきたんです)
長時間かけてはできませんので、
少しずつ続けられる範囲でやろうとしています。
続けるって難しいですよね。
なんとか1ヶ月になりました。
仕事でも同じです。
決めたことをやり続けることは、
なかなか難しいことですが、
お客様が違和感なくお過ごしいただけるように、コツコツと積み上げてまいります。
最近、気になるフレーズです。 コンビニに行きますと、ある特定の商品購入時に いわれます。 「常温ですが、あたためますか?」と。 弁当やおにぎりは、「あたためますか?」なのに、 ある特定商品にかぎり、常温ですが、とつく。 推察するに、弁当やおにぎりは、誰がみても常温、もしくは 冷えているが、その特定商品は、温まっているようにみえるから ではないだろうか? きっと、「あったかいとおもったら、冷えてるやん、これ!」 と、顧客よりクレームを受けたのか、それとも受けるであろうと 予想したのか? 忙しい店員は、弁当においても「あたためますか?」と聞かない 風潮があるが、その特定商品にかぎり、忙しくても必ず聞いてくる。 それは、今すぐ食べるのか?それとも帰ってから自分の都合に合わせて 勝手にあっためるのか、言っとくがあっためないと美味しくないぞ! と選択を迫られている気分になるのは、私だけでしょうか? 被害妄想甚だしいと思われるかもしれませんね。 言葉の捉え方は人それぞれかもしれません。 丁寧に言っているつもりでも、そうとは捉えられないことも あります。 誤解を招くことを恐れて、会話を拒否する人もいます。 言葉とは、知っている言葉の数ではなく、表現に知性を感じるもの です。 簡単な言葉であっても、言い回し方ひとつで大きく変わります。 我々のような仕事では、とくに大切なことかもしれません。 簡単な言葉で、いかにお客様を安心させられるか? 永遠のテーマです。
ここ数日は、梅雨の季節らしく一日中雨が降っていたり、
降ったりやんだりですね。
先日、母と一心寺さんへ行ってまいりました。
10年分のあたらしいお骨佛さまが造立・開眼され、
6月の1か月間は、本堂正面に祀られ「境内出開帳」として
お披露目されています。
私の父も昨年納骨いたしましたので、参拝したというわけです。
平日で雨も降っていましたので、さほど混雑はしておりませんでした。
10年に一度ですから、貴重ですね。
そして、その帰り道、天王寺公園を歩いていましたら、
「林芙美子さんの石碑があると聞いたのですが、どこですか?」と
尋ねられました。ぼんやりと場所を覚えていましたので、お伝えしたところ
「命日なので、お花を・・・」とおっしゃいました。
ファンの方なのだろうと想像しますが、
いつもいつまでも忘れることなくご供養されるお気持ちは貴重ですね。
さて、私たちは現在あたらしいスタッフを募集しております。
少しでも興味のある方は、お気軽にお問合せくださいませ。
雨が降ったり、やんだり
気候の変化が激しく体調を崩しやすい時期
ですが皆様は大丈夫でしょうか?
今朝の、京都の何処かのお寺で
娑羅双樹の花が咲いたというニュースをみました。
御釈迦様に縁のある花だそうです。
きれいな花でした。
後、ふたつ、御釈迦様に縁のある植物があるそうです。
また調べてみようと思います。
本日はご葬儀を終えられたご遺族様から、「いい葬儀が出来て本当に川上さんでお願いして良かったわ」
という大変有り難いお言葉を最後にいただきました。
つい三年半前は、右も左も分からない状態だったこの私が、今ではこのようなお言葉をいただける様になりました。
それもひとえに、一から色々な事を教えてくださった上司並びに諸先輩方、花や粗供養、車両関係など施行に関わる様々な提携会社の方々、そしてなにより私がお手伝いさせていただいた故人並びにご遺族の皆様のお陰でございます。
時には厳しいお言葉をいただき、反省させられる事もございました。まだまだ葬祭業としての経験は浅く、未熟ではございますが、色々な経験を経て成長させていただきました。
今まで関わってきた全ての方々に感謝をし、これからもその経験を活かし、
「一生に一度しかない、やり直しの出来ない最期のお別れの儀式」
という事を十二分に心に刻み、更に成長していけるように日々精進してまいります。
ジメジメとしたむし暑い日が続いております。明日も雨みたいです。最近はこの暑さのせいか、冷たい物を摂りすぎがちになっております。
そのせいか、お腹の調子が良くありません。皆様もお気を付け下さいませ。
さて、本日はご葬儀を担当させていただきました。終わった後に、
「やっぱり事前に相談しておいて良かった。実際その時になったら慌てて冷静ではいられなかったから。でも、まず何をしなければいけないのかを聞いていたので、落ち着いて行動にうつせました」
と仰っておられました。
弊社では、いつでも事前のご相談を受け付けておりますので、何かご不明な事がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせ下さいませ。
最近のニュースを見て思うことですが、
人の生涯は過ごした年数ではなく、どのように過ごしてきたのかが重要だと感じます。
命に保証期間はありませんので、終わりが明日なのか10年先か。それとも50年先か。
その日は誰にもわかりません。
先の見えない不安より、毎日を悔いなく過ごすことが大事だと改めて教えられます。
ふだんは当たり前のように使っているものも使えなくなると不便と感じることはありませんか?
私たちのむの周りにあるパソコン、電話、携帯電話、テレビ、車などほとんどのものがそうですよね。
葬儀でも同じです。
音響設備、施設の設備など当たり前のようですが、使えなくなると大変なことになります。
やはりそうならないように日頃から点検を行い、いつでも使えるように準備しておくことが大切です。
弊社も日程を決めて、備品や、施設の点検を行っております。
いつも、常に、終始というときに「しょっちゅう」という言葉を使います。
お釈迦さまが説法を始められて、60人の弟子ができたときのことです。彼らを集めて「初め善く、中ごろも善く、終わりも善く、道理と表現を兼ね具えた法を説け」と諭されました。
この「初中終(しょちゅうじゅう)」が訛って「しょっちゅう」となりました。
しょっちゅう善く。
常に善いこと素晴らしいことです。
「しょっちゅう」という言葉は善いときに使うのがいいですね。
昨日は雨の音で目がさめるほど
の大雨で通勤時にかなり濡れてしまいました。
今朝のニュースを見ていたら、新幹線が止まり
困った方もたくさんおられた様です。
一部地域では梅雨明けしたとかしないとか・・・。
梅雨があけたら本格的に夏の到来です。
私が一番苦手な季節ですが、
梅雨明けの様な爽やかな気持ちで
仕事に邁進できればと思います
葬儀のスタイルは様々ですが、ご相談を受けていて よく聞きますのが、「何日も会社休めないからな」という言葉。 ご葬儀の打ち合わせでも、「なんとしてでも、今日、明日じゃないと」 と。 学生さんが、テストや入試の日程と重なってしまう、とかのっぴきならない 事情は勿論あることかと思います。 しかし仕事が、というのは大変です。 いろんな立場の方がいらっしゃるでしょうから、何日も休むと 会社が回らないという方もいらっしゃるでしょう。 そんな事情からだけではないでしょうが、葬儀自体がシンプルに なっていくのは、現代の世相を反映しているのでしょうか。 生活しているものの、現状の事情はいろんな意味で優先される べきだと私も思います。 葬儀を軽視しているとは考えたくはありません。 ただし、他人様の葬儀に関心を示さない傾向は強くなって いるような気がします。 入社したばかりの社員だから、責任あるポジションの社員だから、 といっていくと、葬儀のときは忌引きや慶弔休暇があったとしても なんだか、気を使ってしまってどんなポジションのかたも 「そんなに長くは休めない」 こんな風潮はありやしないでしょうか? 冗談話で、会社を休む口実で、「親戚の○○のお葬式でって」 「それはこの前、使っただろ、○○さんとこのおじさんはどうだ?」 なんて現代ではリアル感のない話しなんでしょうね。
梅雨の時期ですが、毎日夏の暑さです。
個人的には洗濯物がサッと乾いて気持ちいいので嬉しいのですが、
この時期に雨があまり降らないと、後にいろんなところへ影響が出そうで、
心配です。明日あたりから雨の天気予報ですので、少しホッとします。
さて、先日友人と話をしていましたら、
去年亡くなったお母様の命日は、ご家族でゆっくりと
生前のことを思い出しながら過ごしたと言っていました。
私も友人から少しは話を聞いていましたが、
結婚してからお母様が施設に入所されるまで同居していたので
色々なことを思い出したのではないでしょうか。
法要は皆の都合にあわせて早めに済ませたようですが、
やはり命日は特別な日です。
1年はアッという間だったでしょうが、お葬式のすぐ後より
今のほうが生前のことをたくさん思い出されるんじゃないかと思います。
お葬式後は何かと忙しいですから。。。