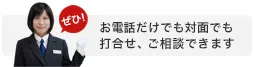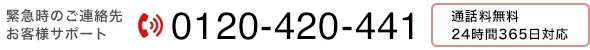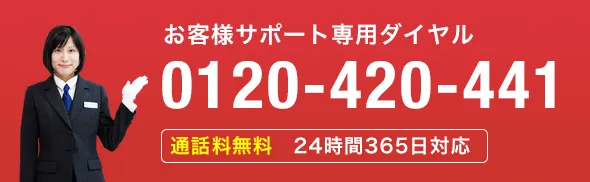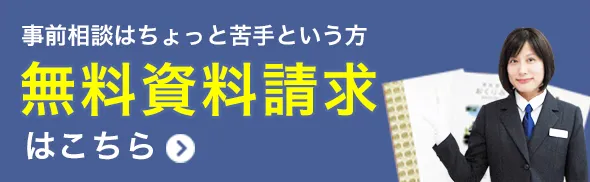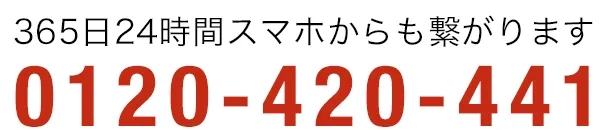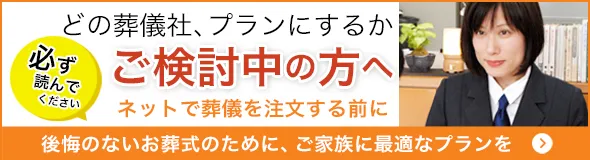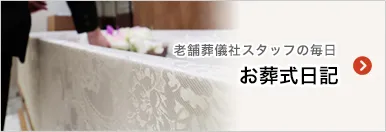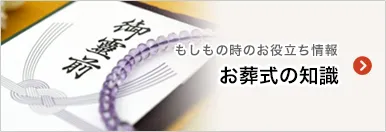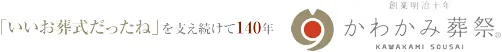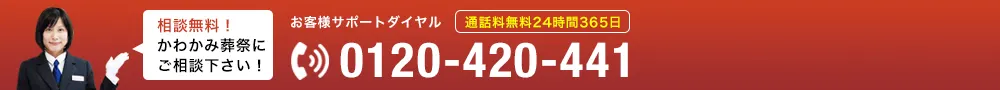北斎場
本日入社して初めての北斎場の見学をさせていただきました。前々から一度見学してみたいと思っていたので、とても勉強になりました。施設内はとても綺麗で故人様との最後の時間を大切に過ごせるかと存じます。見学会なども弊社で行っておりますので、気になる方はお問い合わせくださいませ。
S・Y
バラが綺麗な公園があると会社の方に教えていただき、先日見に行ってまいりました。
場所は堺市立斎場の近くにある東雲公園。
電車ですとJR堺市駅からすぐのところにございます。
駅を出て公園に入ると、満開のバラが出迎えてくれました。
園内には60種類ほどと想像していたよりも多くの品種が植えられており、またバラ園の周りを囲む西洋風の回廊も相まって素敵な雰囲気でした。
平日だったためか人もおらずゆっくりと花を眺めることができました。
色とりどりの花と良い香りに癒された休日でした。
M. M.
当社代表が講師を務めます、お葬式無料講座が福島区民センターで、本日開催されました。
お陰様で満員御礼の盛況ぶりでした。
コロナも5類感染症となり、いろいろな面で緩和されていますが、やはり私たち一人ひとりの気持ちの面での緩和が大きいですね。
旅行もそうですが、お葬式無料講座のように、言ってしまえば行かなくても生活には困らないことに、気兼ねなく参加できるという日常が戻ってきたのだな、と感じました。
5月と6月の講座のテーマは、『家族葬の大失敗』です。
ご興味がおありの方は、お葬式無料情報センター(0120-734-442)までお問合せくださいませ。
Y.F
本日の大阪は、日差しが夏のように熱いですね。。。洗濯物もすぐに乾きそうです。
5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症になりました。ニュースや情報番組でも、アクリル板やアルコール設置台の撤去の様子が流れています。個人や事業者の判断が基本になりますので、対応も様々です。
3月13日からマスク着用が個人の判断が基本となったときは、ほぼ変わらず皆さんがマスクをしていましたが、5月8日以降は徐々にマスクをしない方も増えてきました。私もその一人で、勤務中以外はマスク着用をしておりません。
元々マスクは息苦しくて苦手でしたので、この3年間はつらかったです。
このまま夏に向けて感染症が落ち着いていってほしいと切に願います。
E・I
何をするにしてもタイミングが重視されることは多いです。
少し見誤るとそれ今じゃないと駄目なの? といった事態になったり、このタイミングで!? と不和が生じることも。
葬儀は人の死が関係している分、そういったマナーが特に顕著だと感じます。
例えば枕花も贈るのが早いと死を予知していたとされますし、位牌もそうです。
四十九日までは白木の位牌を置き、それから塗の位牌を用意するのは急な事でまっさらな位牌しか用意できなかったけれどもちゃんとした位牌が届くまで代わりに。といった意味で用意されます。
早ければ悪いことはないとタイミングを計らず先に先にしてしまうと却って失礼にあたってしまう可能性があるのが怖いところです。
ただお互いに気持ち良い関係を築くためにあるマナーですから、分からないではなく、理解しようと勉強を続けていくことが大切なのかなと考えたり。
あまりマナーマナーと目くじらを立てすぎてもお互い疲れますし、さじ加減が難しいところではありますがより良い関係を築けるよう相手の立場を考え動いていけるよう日々精進してまいります。
R.M
今日は母の日でした。
実家にはすでにギフトを送っていますし、
うちの奥さんには少し前に出掛けたときにちょっと良い枕をプレゼントしてました。
さらに昨日休みだったので晩御飯に焼肉をご馳走してます。
しかし、まだ何かを期待するのがいつものうちの奥さんなので
キチンともう何もないからな、と言ってました。
が、仕事からの帰り、まだ花屋さんが空いてる時間だったのでもう買わざるをえません。
財布とにらめっこしながら花屋さんの長蛇の列に並んだ日でした。 J.E
大人の麻疹が2例発生したという記事を読みました。何年か前にも麻疹が流行った時期があり、その当時は妊娠中だったこともあり、抗体があるとはいえ毎日不安な日々を過ごしていたのを思い出しました。感染力が非常に強く、感染者の方が電車の1号車に乗っていても16号車の方まで感染するほどの脅威だそうです。潜伏期間も10日前後との事なので、また今後増えてくるかもしれませんね。コロナが落ち着きマスク着用も緩和されてきましたが、もう少し用心したほうが良さそうです。
S・O
週に1回か2回トレーニングジムに行きます。
そんな激しいトレーニングをしているわけではなく、運動不足解消とアンチエイジング的な感じです。
仕事柄、平日にお休みをいただくことが多いのですが、平日の昼間はおばさま方のピークタイムになっている事が多いです。
毎回、エレベーターに乗る時、おばさま方は私を奥に載せようとします。
扉が開くとモーセの海割りのごとく奥への道ができたりします。
女性更衣室が3階で男性更衣室が4階なのでそうされているのだと思います。
少しでもスムーズにエレベーターが稼働するように考えてるんだなと感心しました。
しかし、「◯◯さん早く!まだ乗れるよ!」と遠くにいる方を待つことも多々あります。
女性心理は難しい。y.y
冬も過ぎて過ごしやすい季節になってきました。
今まではカーディガンを着ておりましたがクリーニングに出してワイシャツで過ごすことが増えてまいりました。
ですがまだ朝晩は涼しくなっておりますので布団から出るのが嫌になっております。
このように寒暖差がある時に体調を崩しやすいですので皆様お気をつけてお過ごしくださいませ。 H.H
ほんとに、今日は暑かったですね。
暑さに慣れていないのか身体がダル重い感じです。
しかし、明日から気持ちを切り替えてバリバリ働きます。sc
私事ながら、今月誕生日を迎えました。
思いがけずプレゼントをいただきました。
祝ってもらう様な歳ではありませんが
嬉しいものです。
よい、1年のスタートになりました。
は、毎年いろいろと変わる時期で、一般的に言うところの3月から4月みたいな感じです。
とても大事な時期ですが、周りからするとそうでもないのかも知れませが、毎年なかなかの圧力を自分にかけているようです。
なるようにしかならない、のはその土台があるからで、土台や基礎がなければ、なるものもならない、が私の考えの根底にあります。
これは仕事に限らず、何かを考えていくさえに、準備や基礎的な知識の習得然り。
その時に慌てて、どうしようもなくなって、それからさらに苦い思いをするのか、余裕ある時期に少しずつでも何かを進めるか、最後の差は大きくつくのではないか、と。
特に凡人はそれが顕著にでるものだ、と。
いつも反省の日々です。
HO
ゴールデンウイーク最終日ですね。皆様におかれましても、どのようにお過ごしになられましたでしょうか?お友達と遊んだり、ご家族との時間を過ごされたりと様々だったかと思います。もし大切な方とのお別れをしなければならなかった際に、そういった思い出を少しずつ紐解いていただければと存じます。そして、その思い出で皆様の悲しみがほんの少しでも和らげればと切実に願っております。
S・Y
新型コロナによる行動制限が緩和され、旅行に行かれる方が増えてきているようですね。
先日も、当社キタ店の周辺を掃除していると「日本一長い商店街はどこにありますか?」と観光客の方に声をかけられました。
キタ店は天神橋筋商店街のすぐ近くにございますので、簡単な道案内をし、お見送りしました。
天神橋筋商店街が日本一長いと聞いたことはあるのですが、実際に端から端まで歩いてみたことはないので、どれくらい長いのかいまいち実感がありません。
出勤時に天満駅からキタ店までの決まったルートしか歩くことがないのですが、その範囲だけでも素敵な飲食店や雑貨屋さんが目にとまります。
一度休日に遊びにきてもいいかもしれないな、と思いました。
M. M.
今日は端午の節句、菖蒲の節句ですね。
今年二度目に、節句の日のブログ担当にあたりました。
前回は3月3日の桃の節句でした。2ヶ月あっという間です。
3月の頃はまだまだ先だと思っていた、家族葬おくりみ勝山のオープンまであと15日となりました。
準備もだんだんと進んでいます。
また最近は、チラシをご覧になった方からの、オープン内覧会のご予約のお電話もいただくようになりました。
5月20日から31日まで、内覧会をおこなっています。ガラポン抽選会などのお楽しみもございます。ぜひご予約の上、お越しくださいませ。
Y.F
本日の大阪は、日差しがありつつもカラッとしておりお出かけされている方も多いのではないでしょうか。
10年以上前に近所に ある葬儀会館が出来た時に、両親は積立をしていたそうで父の葬儀はそちらでお世話になりました。最近までは母も、「自分の時はそこでいいから」と言っていたのでプランとか確認しておいてと話しておりました。
先日、急に解約してきたから書類を記入してと頼まれた時に母に解約理由を聞くと、ご近所さんの評判とのことでした。
あまり解約など一人でできるようなタイプではないのですが、そんな母を動かすご近所さんのクチコミはすごい!と改めて感じました。
E・I
先日弊社で仏具を注文してくださったお客様がおられ、仏具の納品がありました。
届いた仏具はひとつひとつ検品でチェックをするのですが、その時にチェックをしていた上司が、『この仏具しってますか?』と見せて頂きました。
家に仏壇が無い環境で過ごしてきたので、仏具など知らないものばかりで、その見せて頂いた仏具も初めて見るものでした。
【見台】という仏具で、過去帳を置く台のことなのですが、私は学生時代ずっと吹奏楽部をしていたので、自分の中では見台=譜面を置く台でした。今後葬儀の仕事に携わっていると見台=過去帳を置く台と認識も変わってくるのでしょうね。
仏具にもまだまだ知らないものだらけです。お問い合わせにお答えできるよう仏具の勉強もしていこうと思います。
S・O
弊社では年度ごとに個々で目標をたて、達成することでお客様に少しでも貢献できるよう努めています。
今年も目標を立てていく中、去年の自分には見えていなかったこと、
出来るようになったことが見えてきました。
今年は去年の目標を踏まえつつ数年後のことも考え今期の目標をたて、
お客様にお力添えができるよう尽力していければと思います。
R・M
子供二人も大きくなってきたので、車を買い換えようと、
中古ですが今の車より大きな車を購入しました。
大手の中古車販売のお店で買ったのですが、契約して数日後にその販売店が不正などで大炎上してます。
せっかくの新しい車ですか、なんだか不安になってきました。 J.E
今年のゴールデンウィークは1日と2日が平日となっているみたいです。
ですが、私達は仕事の関係上特に関係なく仕事をしております。
ですので、皆さま気にせずご連絡頂ければと思います。
24時間365日いつでもしっかりとご対応させて頂きますのでご安心くださいませ。 H.H