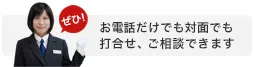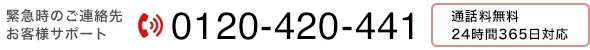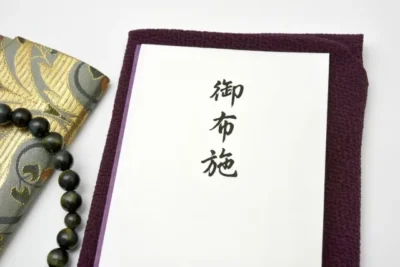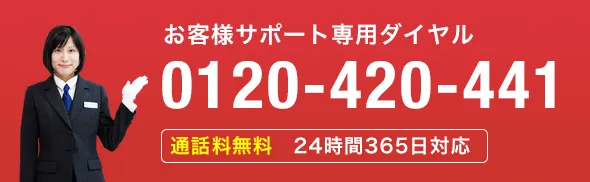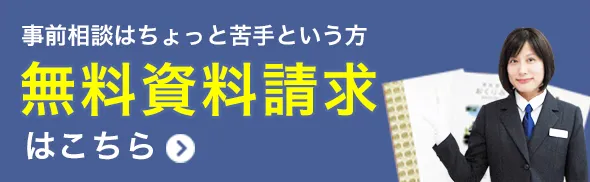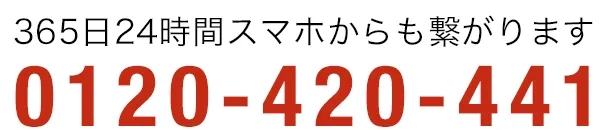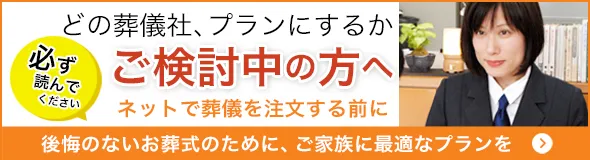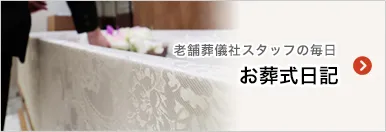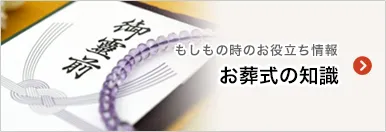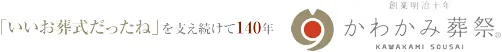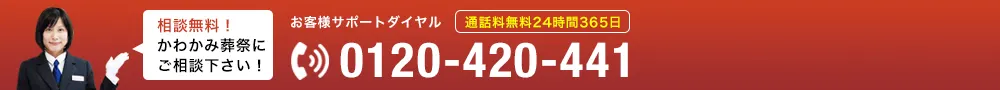葬儀の場では、僧侶に読経や戒名授与のお礼としてお布施を渡します。
その際、お布施を包む封筒に金額や氏名などを書きますが、これには正式な作法があることをご存じでしょうか。
厳かな席で渡すものだからこそ、正しい書き方を覚えておきたいところです。
そこで本記事では、お布施を包む封筒の書き方を、マナーや注意点とともに紹介します。
僧侶への感謝と敬意を正しい作法で伝えたい方は、ぜひご一読ください。
お布施の封筒の書き方
お布施を封筒に包む場合、表面に氏(当家名)を記載するのが一般的です。
また、冠婚葬祭で使用される伝統的な和紙“奉書紙”で、お布施を包む方法もあります。
ただし、奉書紙を使用する場合は、中包み(中袋)を用意しなければなりません。
ここでは、その中袋への書き方についてもあわせて解説します。
表書き
封筒の表面の中央上部には、“お布施”または“御布施”と記載するのが一般的です。
ちなみに正式には“御法禮(ごほうれい)”と書きます。
“読経料”や“戒名料”などの書き方もありますが、お布施は感謝と敬意を示すものなので、“料”という字は使用しないのが一般的です。
中央下部には、喪主あるいは施主の氏名を書きましょう。
その際、フルネームで書くとより丁寧といわれることもありますが、名字のみ、あるいは“○○家”といった書き方でも問題ありません。なぜなら葬儀の場合、その家全体からの御礼であるため、当家名(施主名)で、名字のみ(例:川上家の葬儀なら、「川上」)を書くのが一般的です。
【関連記事】施主と喪主は何が違う?それぞれの役割と決め方とは
裏書き
お布施を奉書紙ではなく封筒で渡す場合は、裏面に住所やお布施として包む金額などを書く必要があります。
裏書きには、左下に郵便番号・住所・氏名・お布施の金額をまとめて書く方法と、お布施の金額のみ右上に書く方法の2種類があります。
記載する項目が多いため、封筒のサイズや文字数、文字の大きさに注意して、見やすく整った配置で書くよう心がけましょう。
ただし、裏書きには、「金額のみ」記入するなど、地域や風習によっても異なってきますので、その地域にあった書き方があるとおもいますので、葬儀社に確認してみてください。
中袋
中袋とは、お布施として渡す紙幣を入れる袋のことです。
表面の中央にお布施として包む金額を旧字体の漢数字で記載し、裏面の左下には郵便番号・住所・氏名・電話番号を書きます。
郵便番号や電話番号を省略することも可能ですが、初めてお会いする僧侶に対しては、これらの情報も書いておくとより丁寧な印象を与えることができます。
旧字体の漢数字の書き方は、次の項で解説しますのでご参照ください。
【関連記事】お布施とは?葬儀を行う地域・宗教別の相場や渡し方を解説
お布施の漢数字の書き方
お布施の封筒に金額を書く際は、旧字体の漢数字を使用するのが正式な書き方です。
たとえば10万円を包む場合、“金拾萬円也”と記載します。
以下に、使用頻度の高い旧字体の漢数字を紹介しますのでご確認ください。
【お布施で使用する旧字体の漢数字】
|
壱(一) |
弐(二) |
参(三) |
伍(五) |
陸(六) |
|
漆(七) |
捌(八) |
拾(十) |
仟(千) |
萬(万) |
上記の表に4と9が含まれていないのは、これらの数字が“死”や“苦”を連想させ、縁起が悪いとされる忌み数であるためです。
お布施として謝礼を包む際には、これらの数字が含まれない金額に調整しましょう。
【宗教別】表書きの書き方
これまでに紹介した封筒の表書き・裏書きや中袋の書き方は、仏式の葬儀における作法となります。
しかし、実際には宗教によって表書きの記載内容が異なるため、注意が必要です。
ここからは、神式とキリスト教式の葬儀における表書きの基本的なマナーをお伝えします。
神式
日本古来の宗教である神道に基づいて執り行われる神式の葬儀では、表書きに“御祭祀料”または“御初穂料”と書くのが一般的です。
祭祀には「儀式を執り行ってもらう」という意味があり、神社や神主への謝礼として御祭祀料を包みます。
なお神式の場合も仏式と同様、封筒の表側の中央上部に御祭祀料または初穂料と書きましょう。
【関連記事】神式の葬儀マナーを徹底解説!
キリスト教式
キリスト教式の葬儀の場合、表書きには“献金”あるいは“謝礼”と記載します。
基本的な考え方は仏式のお布施と同様で、教会や神父、牧師への感謝の気持ちとして謝礼金を渡します。
教会に奉納する場合は“献金”、神父や牧師に渡す場合は“謝礼”と書くのが一般的です。
そのほか、キリスト教の教派によっても書き方が異なります。
たとえば、カトリックでは“御ミサ料”、プロテスタントでは“記念献金”と記載することもあります。
【関連記事】キリスト教の葬儀の流れやマナーを徹底解説
お布施の封筒を書く際の注意点
ひと口にお布施といっても、宗教によって表書きの書き方に違いがあることがわかりました。
では実際に、封筒の表書きや裏書き、中袋に氏名や住所などを書く際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
以下では、お布施を入れる封筒に記載する際に覚えておきたい2つの注意点を紹介します。
注意点①封筒の表書きは濃い墨で書く
お布施を入れる封筒の表書きは、筆や筆ペンなどを使い、濃い墨で書くのが基本的なマナーです。
薄墨は、故人の訃報を受けた悲しみを表す意味があり、葬儀を行うご家族に渡す香典袋に記載する際には適しています。
しかし、お布施は僧侶に対する感謝や敬意を示すものであるため、薄墨ではなく濃い墨を使うのが適切です。
【関連記事】葬儀で包む香典の金額の相場は?渡す際のマナーも紹介
注意点②原則としてボールペンは使用しない
お布施の封筒の表書きは、濃い墨を使用するのがマナーであるため、ボールペンで書くと失礼にあたります。
毛筆を使うのが理想ですが、毛筆が苦手な場合や手元にない場合は、市販の筆ペンを使用するとよいでしょう。
ただし、裏書きや中袋に氏名や住所、金額などを記載する際は、ボールペンを使用してもマナー違反とはなりません。
裏書きや中袋は文字数が多く、毛筆や筆ペンでは読みづらくなるおそれがあるためです。
表書きは墨で記載し、裏書きや中袋は読みやすさを考慮してボールペンを使用するのもよいでしょう。
お布施の封筒はどれがよい?
お布施を包む際は、厚手で郵便番号欄がない白無地の封筒が適しています。
薄手の封筒は中の紙幣が透けてしまう可能性があるため、お布施の封筒には向いていません。
お布施を入れる封筒は、水引の有無によって大きく2種類に分けられますが、迷った場合は水引なしの封筒をお選びください。
お布施の正しい包み方
お布施の封筒の書き方や選び方を確認したところで、続いては、お布施の正しい包み方を解説します。
この項では、封筒に包む場合にくわえて、奉書紙を用いる場合についてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
白い封筒に包む場合
白封筒を使用する場合は、紙幣の向きを揃え、封筒の表面の上部に肖像画がくるように入れましょう。
その際、二重の封筒は“不幸が続く”と連想されるため、中袋は使わずに紙幣を直接封筒に入れるのがマナーです。
奉書紙で包む場合
奉書紙を使用する際は、まず紙幣を半紙で包み、中包みを作ります。
その際、表書きの上部に紙幣の肖像画がくるよう向きを揃えて入れるのが基本的なマナーです。
奉書紙で中包み(中袋)を包む際の手順は、以下の通りです。
【奉書紙でお布施を包む際の手順】
- 奉書紙を縦に置き、中袋を中央よりやや左に置く
- 左側から中袋を包み込むように谷折りする
- 続いて右側からも谷折りする
- さらに上下から谷折りする
上記の手順に沿って丁寧に折ることで、しわなくきれいな仕上がりになります。
お布施の包み方は地域で異なる
お布施を包む際は、水引のない封筒を使用するのが一般的です。
水引には、魔除けや故人の供養といった意味がありますが、お布施は僧侶に対する謝礼なので必要ありません。
ただし、地域によっては水引を使用する習慣があり、たとえば関西地方では、黄色と白の水引を使用します。
同じ関西圏でも、奈良県では白黒の水引を使用することがあります。
このように、お布施に使用する封筒の水引の有無や色は地域によって異なるため、お住まいのエリアのルールを事前に確認しておきましょう。
【関連記事】お布施の相場はどれくらい?葬儀と法要別に紹介
お布施の意味を理解し、正しい封筒の書き方を心がけましょう
今回は、お布施を入れる封筒の正しい書き方に焦点を当てて解説しました。
お布施を封筒に入れて僧侶に渡す場合は、表面と裏面に必要な情報を記載します。
原則として、表書きは毛筆や筆ペンで記載しますが、文字数が多くなりがちな裏書きは使い慣れた筆記用具を使用してもマナー違反とはなりません。
また裏書きに金額を記載する際は、一般的な漢数字ではなく、旧字体で書くことも覚えておきましょう。
大阪市の生野区、東住吉区、天王寺区にお住まいで、お布施に関するお悩みがある方は、かわかみ葬祭にご相談ください。
経験豊富なスタッフが丁寧に対応し、ご家族の希望に沿った最適な葬儀プランをご提案いたします。