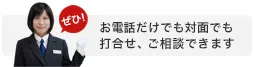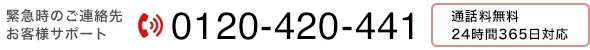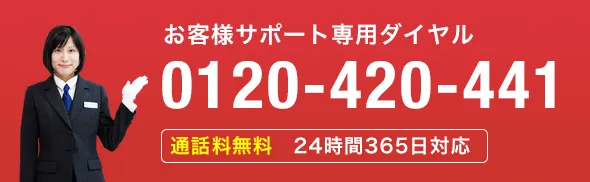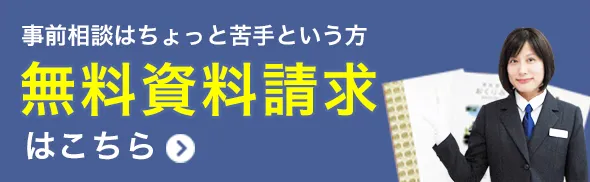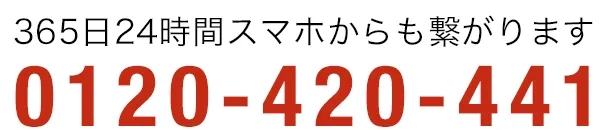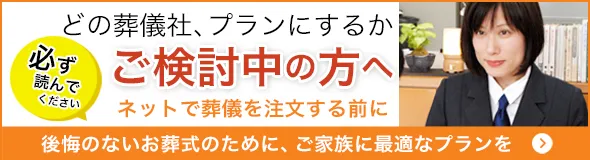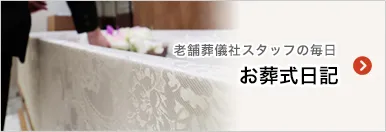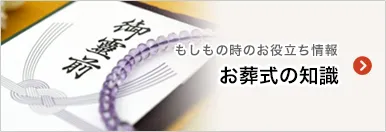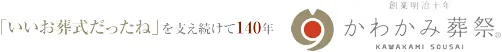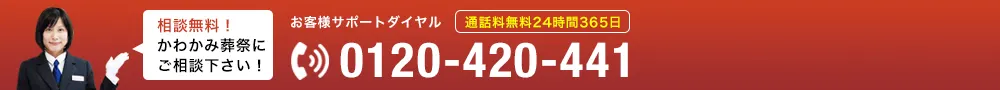葬儀のマナーは、宗教や宗派によって異なります。
日本で行われる葬儀の大半が仏式(仏教)であることから、神式の葬儀に参列するとなると、どういったマナーや作法があるのか、わからないことも多いでしょう。
そこで本記事では、なじみの薄い神式の葬儀マナーを徹底的に解説します。
葬儀中も落ち着いて対応できるよう、必要な知識を身につけておきましょう。
神式の葬儀の特徴
神式の葬儀は、日本古来の民族宗教“神道”に基づいた儀式であり、“神葬祭”ともよばれます。
亡くなった家族を先祖とともに“守り神として奉る”ことを目的としており、故人の魂を極楽浄土へ送り出す仏式の葬儀とは意味合いが大きく異なります。
そのため神式の葬儀では、別れを惜しむというよりは、故人が神となることを前向きな気持ちで祈るといった趣があるわけです。
また、神道では人間の死をけがれと考えており、葬儀を通してけがれを祓い、日常の生活に戻すという目的もあります。
神聖な場所でけがれを扱うことを避けるため、葬儀は神社ではなく自宅や葬儀会場で行うのが一般的です。
【関連記事】キリスト教の葬儀の流れやマナーを徹底解説
神式の葬儀の流れ
神式の葬儀は、亡くなった翌日から2日間にわたって執り行われます。
基本的な神式の葬儀の流れを表にまとめました。
一般的な神式の葬儀の流れ
| 工程 | 詳細 | |
| 逝去当日 | 1.帰幽奉告(きゆうほうこく) | ・自宅の神棚や祖霊舎(それいしゃ:先祖を奉る祭壇)に、家族が亡くなったことを報告する・先祖の霊が死者のけがれに触れないよう、神棚の正面に半紙を貼る |
| 2.枕直しの儀 | ・故人に白小袖を着せ、白い布で顔を覆う・北枕にして安置する・故人のそばに祭壇を設け、米や塩、水や日頃好んで口にしていた物を供える | |
| 3.納棺の儀 | ・遺体を清め、死装束を着せる・棺に遺体を収める | |
| 葬儀1日目 | 4.通夜祭 | ・故人の安らかな眠りと、家族の家を守っていただくことを願う・斎主(仏式でいう僧侶)が祭詞と祭文を奏上し、演奏者が雅楽を奏でる・玉串を奉って拝礼する(玉串奉奠:仏式の焼香にあたる儀式) |
| 5.遷霊祭(せんれいさい) | ・故人の魂を身体から抜き、霊璽(れいじ)に移す・魂が動くとされる夜を再現するため、部屋の明かりが消される・御霊移し(みたまうつし)ともよばれる | |
| 葬儀2日目 | 6. 葬場祭 | ・弔辞奉読や祝詞奉上が行われる・玉串を奉って拝礼する(玉串奉奠) |
また、神式の葬儀を終えて一定の日数を経ると、仏式の法要にあたる“霊祭”や“式年祭”が執り行われます。
十日祭や五十日祭などのように、死後100日までのあいだに行われる儀式を霊祭、1年目の命日以降の儀式を式年祭といいます。
こうして流れを見てみると、神式と仏式で似た部分があると思われたかもしれませんね。
神式の葬儀マナー

ここまで仏式の葬儀の概要を解説しましたので、以降は具体的な神式の葬儀のマナーを紹介していきます。
神式の葬儀に参列する機会はそう多いものではありませんが、基本的なマナーを知っておけば当日に慌てることはないでしょう。
服装
神式の葬儀に参列する際の服装は、仏式の葬儀と同じ喪服で問題ありません。
ただし、喪服は“正喪服・準喪服・略喪服”と3つの格式に分かれており、ご自身がどれを着用すべきか配慮する必要があります。
喪服の格式と詳細
| 喪服の格式(着用者) | 男性 | 女性 |
| 正喪服(喪主・遺族) | ・和装・モーニングコート | ・和装・ブラックフォーマル |
| 準喪服(喪主・遺族・参列者) | ・ブラックスーツ | ・ブラックフォーマル |
| 略喪服(参列者) | ・黒、紺、グレーなどのダークスーツ | ・黒、紺、グレーなどのアンサンブル |
葬儀に参列する際の服装は、準喪服が基本です。
正喪服は、喪主や配偶者など故人の近親者が着用する物であり、知人や友人として参列する方は、それより格式の低い喪服を選ばなければなりません。
また、靴下やストッキング、ネクタイやバッグ、靴などもすべて黒で合わせ、結婚指輪以外のアクセサリー類はできるだけ外しておきます。
仏式と同様、殺生を連想させる爬虫類の素材を使ったバッグや靴、毛皮のコートなどはお控えください。
もし、喪服の用意が間に合わない場合は、黒や紺、グレーといった地味な色合いの略喪服(平服)で代用することもできます。
その際、男性はネクタイも、スーツと同じく地味な色合いの物を着用しましょう。
なお、仏式の葬儀と違い、神式の葬儀では数珠は不要です。
【関連記事】葬式に着ていって良い服・悪い服とは?男女別に詳しく紹介
【関連記事】お葬式に適した女性の服装と、マナーを守った着こなし方
挨拶の言葉
先述のように、神式の葬儀と仏式の葬儀では死生観が異なるため、親族に対する挨拶の言葉も異なります。
神式の葬儀は、故人が家を守る神となることを祈る儀式であり、死を悼むためのものではありません。
そのため、仏式の葬儀で用いられる「お悔やみ申し上げます」「ご冥福をお祈りします」などの悲しみを表す挨拶はしないようご注意ください。
そのほか「成仏」「供養」「弔う」といった言葉も、避けたほうがよいでしょう。
神式の葬儀において、親族に言葉をかける際は「御霊(みたま)のご平安をお祈りします」と伝えるのが正解です。
より丁寧な言い回しをするのであれば、「ご帰幽の報に接し心からお悔やみ申し上げますとともに、御霊の安らかに鎮まり給うことをお祈り申し上げます」となります。
【関連記事】親族のみで執り行う葬儀での食事代はどのくらい必要?
手水の儀
神道の祭式では、手や口をすすぎ身のけがれを清める“手水(ちょうず)の儀”を行います。
葬儀場に入る前や葬儀から帰宅する際に行う儀式であり、その所作はマナーとして覚えておきましょう。
【手水の儀の所作】
1.右手で柄杓を持ち、桶から水を汲む
2.左手に水をかける
3.柄杓を左手に持ち替えて、右手に水をかける
4.柄杓を右手に持ち替えて、左手に水を注ぎ、口をすすぐ
5.左手に水をかける
6.柄杓をもとの位置に戻す
7.懐紙かハンカチで手と口を拭く
地域によって所作が異なるケースもありますが、この流れが基本となります。
最近では手水の儀が省略されることもあるようですが、葬儀場に道具が用意されている場合は必ず行います。
玉串奉奠
玉串奉奠(たまぐしほうてん)は、神式の葬儀に際して複数回にわたり行われる儀式です。
仏式の葬儀における、ご焼香にあたるものとご承知おきください。
神が宿るとされる榊(さかき)に紙垂(しで)や麻を結び付けた“玉串”を、祭壇に奉納します。
玉串奉奠の所作は、以下の通りです。
【玉串奉奠の所作】
1.遺族と斎主に一礼し、玉串を受け取る
2.玉串を胸の高さに捧げ、祭壇の前に進む
3.祭壇に一礼し、玉串の枝が手前に来るよう時計回りに90度回転させる
4.左手に枝、右手に葉先がくるように玉串を持ち替える
5.玉串を時計回りに180度回転させ、枝を祭壇に向けて供える
6.一歩後ろに下がる
7. 2回、深く礼をする
8. 2回、音をたてないように拍手する(しのび手)
9.深く礼をする
10.正面を向いたまま2~3歩下がる
11.遺族と斎主に一礼し、退出する
玉串奉奠で押さえておきたいことは、玉串の受け取り方と拝礼の2点です。
玉串を受け取る際は、右手で上から枝をつまむようにし、左手で下から支えるように葉先を持ちます。
また神式の拝礼では“二礼二拍手一礼”を基本とし、拍手は音を立てずに両手を打つ“しのび手”で行うことがマナーです。
神式の葬儀の香典

神式の葬儀では、香典の代わりに“玉串料”としてお金を渡すことが一般的です。
包む金額の相場や、使用する香典袋に違いがあるのか、気になる方も多いでしょう。
それぞれ以下で詳しく解説します。
金額
玉串料の金額の相場は、仏式の葬儀の香典と変わりありません。
玉串料の相場は、以下の表をご参照ください。
| 故人との関係 | 金額の相場 |
| 両親 | 3万~10万円 |
| 兄弟・姉妹 | 3万~5万円 |
| 祖父母 | 1万~3万円 |
| 叔父・叔母 | 1万~3万円 |
| そのほかの親戚 | 5,000~1万円 |
| 会社関係者 | 3,000~5,000円 |
| 友人 | 3,000~5,000円 |
玉串料として包む額は、ご自身の年齢が高くなるにしたがって、金額も高くなるのが一般的です。
また、“縁が切れるから縁起が悪い”という意味から偶数を避け、割り切れない数字である奇数に合わせた金額を包むのがマナーです。
【関連記事】葬儀で包む香典の金額の相場は?渡す際のマナーも紹介
香典袋の種類
玉串料は、香典と同じく香典袋に包んでお渡しします。
使用する香典袋は、包む金額に応じて水引の種類を選ばなければなりません。
金額に適した香典袋(水引)の種類
| 香典袋(水引)の種類 | 包む金額 |
| 水引が印刷されている香典袋 | 3,000~5,000円 |
| 白黒の水引がかけられている香典袋 | 5,000~3万円 |
| 双銀の水引がかけられている香典袋 | 3万円~ |
玉串料が高額になるにつれて、より豪華な香典袋を使用します。
基本的には5本の水引で結われている物を使用しますが、10万円を超える額を包む場合は、双銀の装飾性が高く10本の水引で結んである物がよいとされています。
ただし、偶数である10本の水引は避けるべきと考える地域もあるので、その点の配慮は必要です。
また、香典袋によっては蓮の花や十字架がデザインされた商品もありますが、これらは仏式やキリスト教式の物です。
このような装飾が施された物は神式の葬儀には不適切なため、無地の香典袋をご購入ください。
表書きの書き方
神式の葬儀に持参する香典袋の表書きには、“御神前”と書くのが一般的です。
そのほか、“御玉串料”“御榊料”“御神饌料”と記入することもできます。
なお、宗教の違いを問わず使用できる“御霊前”と書いても問題はありませんが、亡くなってからの日数に応じて、言葉を使い分ける必要があります。
神道では故人は死後50日を経て神になると考えられているため、50日以降の霊祭や式年祭に際しては、香典袋の表書きには御神前と記入するのが正しい作法です。
香典袋の包み方
神式の香典袋の包み方は、仏式のときと同じです。
中包みに対して、紙幣の肖像画が裏面、下側になるように合わせて封入します。
封入する紙幣は、新札やシワだらけの物を避け、適度に折り目のついた古札を用いるのがマナーです。
これは、新札は不幸を前もって予測し用意していたことを暗示させ、シワだらけの紙幣はみすぼらしいと感じ取られてしまうためです。
新札しか用意できない場合は、紙幣の端に少し折り目をつければ問題ありません。
紙幣を封入したら、薄墨の筆ペンを使い、中包みに漢数字で金額を記入しておきましょう。
神式の葬儀では一般的な葬儀と挨拶が異なる
今回は、神式の葬儀マナーを解説しました。
神式の葬儀は、仏式の葬儀とは異なり、故人を先祖とともに守り神として奉ることを目的とした儀式です。
そのため、一般的な葬儀で用いられる「お悔やみ申し上げます」といった挨拶は避け、「御霊のご平安をお祈りします」と伝えるのがマナーとされています。
また、手水の儀や玉串奉奠など、神式の葬儀ならではの儀式もあるため、スムーズに振舞えるよう基本的な所作を覚えておくことをおすすめします。
大阪で、神式の葬儀に対応できる葬儀社をお探しなら、かわかみ葬祭にご相談ください。
創業140年を超える年月で培ってきた経験とノウハウを活かし、安心して葬儀を進められるようサポートいたします。